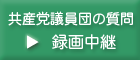2010年区議会第二回定例会
日本共産党区議団質問
日本共産党区議団の代表質問2010年6月9日
質問者 沖島えみ子 議員

日本共産党区議団の一般質問
2010年9月17日
質問者 星野たかし 議員

提出議案等
(略)
2010年区議会第2回定例会での質問
2010年6月9日質問者 沖島えみ子 議員
1.公契約条例制定について
2.特別養護老人ホームの増設について
3.保育園の待機児童解消について
4.保育料の軽減について
5.後期高齢者医療制度の廃止について
6.難聴者への磁気ループ(専用受信機を含む)の設置を求める質問
7.孤独死をなくすために質問
8.旧国立保健医療科学院跡地の活用について
9.子宮頸がんワクチンについて
10.ヒブワクチンについて
11.小児用肺炎球菌ワクチンについて
12.CTやMRI、脳ドックの検査費用の助成実施ついて
13.特定不妊治療費助成に関する質問
14.地上デジタル化について
15.品川駅東西自由通路の安全確保について
16.家賃助成制度の復活・拡充について
17.ちぃばすの改善について
18.学校図書館について
19.蔵書の充実について
2010年第2回港区議会定例会で日本共産党港区議団を代表して区長、教育長に質問いたします。
昨年の総選挙で、「政治を変えたい」という国民の強い意識によって政権が交替しましたが、普天間基地問題、雇用や社会保障、政治とカネの問題など、あいつぐ公約違反と逆走に対する国民の怒りの中、鳩山内閣は総辞職に追い込まれました。新内閣が発足しましたが、いくら内閣が変わっても国民の立場にたった政治をしなければ、国民の信頼に応えることはできません。
私たち日本共産党は、今の政治をおおもとから切り変える改革提案を行っています。
一つは、あまりにも行き過ぎた財界・大企業よりの政治を正し、大企業に雇用や社会保障の責任を果たさせる、まともなルールをつくる。
もう一つは、アメリカいいなりの政治を正し、堂々と国民の立場でものを主張する政治に切り変える。という2つの改革提案です。
例えば、財源の問題では、どこから税金を集め増収をはかるのか、大企業に応分の負担を求めるのか、消費税増税で国民に負担を求めるのか。
雇用では、派遣労働を禁止して正社員が当たり前のルールをつくるのか、大企業の要望を受けて派遣労働を温存してしまうのか。
基地の問題では、アメリカに無条件基地撤去を要求するのか、沖縄や徳之島に基地の強化を押しつけるのか。
どの問題でも財界とアメリカいいなりの政治=2つの政治悪にぶち当たります。財界・アメリカ向けの政治か、国民本位の政治か、どちらの方向を向いた政治をするのかが、鋭く問われます。
現政権党も、旧政権党も、またいくつもできた「新党」も、2つの異常な政治を改革する立場に立てず、国民本位の政治への転換を主張しているのは日本共産党だけです。
この問題は、7月の参議院選挙でも、最大の焦点・争点となる問題です。私たちは、本当の政治改革、国民本位の政治実現に向け全力で奮闘する決意を表明し、質問に入ります。
1、公契約条例制定について
初めに、公契約条例制定について質問します。
千葉県野田市は、今年2月1日から、全国初の公契約条例を施行しました。
これまでの発注は、入札で一番価格の低い業者と契約していましたが、安すぎることで、品質が確保できなくなったり、従事する労働者の賃金が低下したり、下請業者にしわ寄せがされる懸念がありました。
市は、平成17年に、国に公契約法制定を要望したのに、国はやろうとしません。国を動かすためにも先駆的に条例化したのです。
条例が対象とする契約は、建設工事は予定金額が1億円以上のもの、業務委託は、予定金額が1,000万円以上のうち、施設の設備や機器の運転・管理、保守点検、施設の清掃です。
建設工事は、国が公共工事の積算に用いる労務単価を、業務委託は、市の技能労務職・用務員の賃金から計算したものを市の定める最低賃金とし、受注者や下請業者などに最低賃金以上での賃金保障と周知義務を課し、条例違反には立入検査と是正命令、契約解除も規定。さらに、実績や技術者の資格なども総合的に評価し、落札者を決定する総合評価方式や、指定管理者の候補者の選定でも賃金を評価しています。
私たちは、昨年第四回定例会で、港区でも公契約条例を制定せよと提案しましたが、区は野田市の条例について、「所管では承知しているが、さらに詳細について検討していく」と答えています。どのような調査と検討をし評価したのか、答弁を求めます。
野田市は、国を動かすために、先駆的に条例化した、と経過を述べています。港区も、この間の関係委員会での質疑で、契約における労働条件の設定などは、本来国がやるべき問題と答えています。その立場からも、まず、国に対して、公契約法制定を要望すべきです。答弁を求めます。
そうした取り組みと平行して、区として、契約における下請単価や賃金の最低限の基準をとり込んだ、公契約条例を制定すべきです。
答弁を求めます。
【副区長答弁】ただいまの共産党議員団を代表しての沖島えみ子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、公契約条例についてのお尋ねです。
まず、公契約条例についての調査、検討及び評価についてです。区では、現在、野田市の公契約条例や公契約法をめぐる国の動き、また関連法令などにより、状況の把握に努めております。公契約条例制定に際しては、適正な労働条件についてのとらえ方、労働条件の内容への介入の是非、規制する賃金水準のあり方、中小事業者を含む企業への影響など、解明、解決すべき難しい課題もあります。今後も、引き続き情報収集を行うなど研究を続けてまいります。
次に、公契約法の制定を国へ求めることについてのお尋ねです。
労働条件は、事業主と労働者との間で決められることが基本であり、最低賃金法や労働基準法等、国全体の法制度の中で整理されているものです。区としては、現在、国に対して公契約法の制定を求めていくことは考えておりません。
次に、公契約条例の制定についてのお尋ねです。
労働条件は、事業主と労働者との間で決められることが基本です。また、最低賃金法や労働基準法等の法律を踏まえ、国全体の制度の中で遵守されるべきものと考えております。区が発注する契約においては、工事等の適正な履行を確保するとともに、下請を含め労働者の労働条件が守られることが重要です。区では、工事受注者に対して、労働関係法令を守ること、また、下請契約の際に代金を適正に支払うことなどを文書で周知していることから、公契約条例の制定は考えておりません。
2、特別養護老人ホームの増設について
介護保険制度がスタートして10年がたちました。社会全体で介護をにない、保険料を払えば誰もが必要なサービスを受けられるとしていましたが、実態は受けられません。
4月から入所がはじまった「ありすの杜」は、特別養護老人ホーム定員200床に対し、600人を超えるひとたちが入所を申し込みました。新しいホームが開設しても400人が入れません。
「ありすの杜」は、全室ユニット型のため利用料が高く、生活保護の人は入れません。
今までは、ユニット型でないと国は補助金をだしませんでしたが、改訂されました。個室ではなく、2人部屋、4人部屋を希望する人もいます。
低所得者も入れる多床室を含む特養ホームを早急に設置すべきです。
答弁を求めます。
すでに9割を超える人の入所が終わりましたが、介護度の平均は3.8、入所者のうち医療対応の必要な人は約15~20%です。指数が高い人から順に番号がつけられ入所が決定しますが、本来入れるはずなのに、78名が医療対応のため、入所不可となりました。介護度4~5の人でも医療対応が必要な人は入所が困難です。
必要な職員体制をとり、医療対応が必要な人の入所枠を全てのホームで増やすべきです。そのために施設の要望を聞き、実態にあった区としての人的支援、財政支援を行なうべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、特別養護老人ホームの増設についてのお尋ねです。
まず、多床室を含む特別養護老人ホームの早急な設置についてです。区は、特別養護老人ホームの整備を計画的に進め、ありすの杜南麻布の二百床の施設整備により、合計七百十一床のベッドが確保されました。今後の建設計画につきましては、ありすの杜南麻布の申し込み者の状況や、高齢者人口、要介護認定者数の推移を見定め、入所希望者の実態把握に努めるとともに、ケアハウスやグループホームなどの住宅系施設なども含めた高齢者の多様な住まいについて、実態及びニーズに関する調査を行い、港区高齢者保健福祉計画改定の中で検討してまいります。
次に、医療対応が必要な人の入所枠をふやすことについてのお尋ねです。
現在、港区内の特別養護老人ホームでは、平均でも、定員の四分の一を超える医療対応が必要な要介護高齢者の受け入れを行っております。区としては、医療対応が必要な要介護高齢者をより多く受け入れるために、区立特別養護老人ホームに国基準以上の看護師を配置するなど、現在もさまざまな支援を行っております。しかし、特別養護老人ホームは病院とは異なる施設であることから、対応できる医療行為や受け入れ人数には限界があります。このようなことから、現段階において、医療行為が必要な方の入所枠をふやすことや、特別養護老人ホームの今以上の人的支援、財政支援を行うことは考えておりません。
3、保育園の待機児童解消について
雇用破壊が子育て世代を直撃し、2人で働かなければ生活が出来なかったり、仕事と子育てを両立しようとする女性が増え保育需要が増え続けています。しかし、認可保育園をつくろうとしなかったため、待機児童が増え続けています。
「育児休暇が切れるというのに、保育園が見つからない」、「自営業だから入れなかった」、「双子がどちらも入所できなかった。そのため認可外保育所の保育料が20万円以上にもなってしまう。これでは生活が大変」という深刻な声が私たちに寄せられています。保育園の待機児童数は年度当初の4月でも1,000人近くが(912人)を超え、入所できない状況でした。
国が保有する未利用の土地や建物を有効活用するため、財務省は保育園や介護施設などへ売却だけでなく貸し出しをするという方針を出しました。
東京都も低い賃料で社会福祉施設建設への土地を貸し出している例もあります。
待機児童解消にむけ、
1.区内の国公有地の未利用地を活用し、認可保育園を建設すること。
2.緊急暫定保育施設をひきつづき建設すること。
3.(暫定)東麻布保育室を継続すること。
4.(仮設)高輪保育園をひきつづき使用すること。
5.現在地の志田町保育園用地の活用は、保育施設を盛り込むこと。
答弁を求めます。
【答弁】次に、保育園の待機児童解消についてのお尋ねです。
まず、区内の国公有地の未利用地を活用した認可保育園の建設についてです。区は、これまでも待機児童解消に向け、認可保育園三園の整備、五園の改築及び民間の土地取得や都有地の活用などにより、緊急暫定保育施設の整備や認証保育所の誘致を進めてまいりました。現在も、緊急暫定保育施設等に適した国公有地を調査しておりますが、現段階では適当な用地がありません。今後とも、待機児童の地域的状況等を分析し、国公有地等の活用について検討してまいります。
次に、緊急暫定保育施設の増設についてのお尋ねです。
緊急暫定保育施設については、区内五番目となるたまち保育室を六月一日に開設いたしました。さらに現在、芝浦港南地域において認証保育所の誘致を進めており、これにより大幅な待機児童の解消を見込んでおります。しかしながら、保育需要は社会経済状況に左右される側面があり、予断を許さない状況にあると考えております。さらなる緊急暫定保育施設の設置につきましては、待機児童の状況を見極め、必要に応じて検討してまいります。
次に、東麻布保育室の継続についてのお尋ねです。
現在、東麻布の緊急暫定保育施設は、旧飯倉小学校の校舎を利用した施設で、平成二十四年三月までの予定で運営しております。東麻布保育室の継続につきましては、待機児童の状況を見極め、必要に応じ継続について検討してまいります。
次に、(仮設)高輪保育園の継続使用についてのお尋ねです。
現在、高輪保育園を含め、認可保育園五園の改築による定員拡大を図っております。高輪保育園は、東京都の土地を活用し、仮設を設置しているものです。仮設の継続使用には課題もあり、慎重な検討が必要ですが、施設の取り扱いや借用期間の延長など検討しているところです。今後も、引き続き継続使用の方策を検討し、待機児童の解消に努めてまいります。
次に、志田町保育園移転後の跡地活用についてのお尋ねです。
志田町保育園移転後の跡地活用につきましては、白金地域における区有施設整備上の課題を解決するために、有効に活用してまいります。
4、保育料の軽減について
渋谷区が所得400万円以下の世帯の保育料を無料にし、1千万円以下の世帯の保育料を所得に応じて減額しました。私たちは第2子以降の保育料無料化と合わせ、保護者への負担軽減を図るため、渋谷区の例を参考に港区でも実施をと前定例会で質問しました。
答弁は、「保護者の就労希望の増加とそれに伴う入園希望者の急増により、待機児童の解消になっていないから保育料の減額や無料化は考えていない、第2子以降についてはすでに減額しているからさらなる減額は考えていない」というものです。
「待機ゼロ」という自らの約束を守らず、待機児童がいることを保育料を軽減しない口実にすることは許されません。
子どもは社会の宝、保護者の負担軽減という観点にたち渋谷区などの先進区を参考に保育料の軽減を図るべきです。
1.認可・認証保育園、認可外保育園の保育料を所得400万円以下の世帯については無料にすること。所得1千万円以下の世帯の保育料を段階的に減額すること。
2.第2子以降の保育料を無料にすること。
答弁を求めます。
【答弁】次に、保育料の軽減についてのお尋ねです。
まず、世帯の収入に応じた保育料の軽減についてです。保育園の待機児童については、緊急暫定保育施設の整備や認証保育所の誘致により、大幅な解消を見込んでおります。しかしながら、昨今の社会経済状況を背景とした保護者の就労希望の増加もあり、現在のところ、待機児童の解消には至っておらず、定員の拡大が重要課題と考えております。こうした現状においては、認可保育園、認証保育所及び認可外保育園の保育料の減額及び無料化は、現在のところ考えておりません。
次に、第二子以降の保育料の無料化についてのお尋ねです。
認可保育園での保育料は、第二子以降の方には所得に応じた減額を行っており、さらなる保育料減額は現在のところ考えておりません。
5、後期高齢者医療制度の廃止について
75歳という年齢で差別する、後期高齢者医療制度への怒りは、とどまるどころか民主党の公約違反とあいまって大きく広がっています。
Aさんは、昨年10月で75歳になり、保険料の納付書が送付されてきました。2割軽減でも1回の金額が3,860円で、とても払えません。
同居している息子さんは、病気で働けないために、年金収入の中から息子さんの国民健康保険料を優先して支払い、自分の分は後回しにしていました。
10月までは、同一世帯ですから国民健康保険料だけですんでいたのに、75歳になったとたん、経済状況は変わらないのに保険料負担が増え、Aさんは区から督促状が来るたびに悩んでいました。
現在、納付相談をして1回の支払いを引き下げてもらっています。
民主党政権が検討している新制度は、65歳以上の高齢者を別勘定の国民健康保険に加入させるうばすて山の入山年齢を拡大する改悪です。
民主党は、野党時代、後期高齢者医療制度は高齢者を差別するひどい制度だと、私たちと一緒に廃止法案を参議院に提出しました。このひどい制度を続けること自体が、国民には信じられないことです。
後期高齢者医療制度は、廃止するよう 国に求めるべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、後期高齢者医療制度の廃止についてのお尋ねです。
国は、後期高齢者医療制度を制止し、高齢者医療制度改革会議のもと、新たな高齢者の医療制度の具体的なあり方を検討しております。こうしたことから、国に制度の廃止を求めることは考えておりませんが、区民生活にどのような影響があるのか、情報収集に努めるとともに、国の動向を注意深く見守り、適切に対応してまいります。
6、難聴者への磁気ループ(専用受信機を含む)の設置を求める質問
次に、難聴者への磁気ループ(専用受信機を含む)の設置を求める質問です。
難聴者は約600万人とも言われ、今後も増加が予想されます。
難聴者は、通常補聴器で聴力を補っていますが、騒音の多い屋外や人の多く集まる場所では音声が聞き取りにくくなります。
磁気ループは、音声記号を磁気に置き換えて、磁気ループに対応できる補聴器に伝えるシステムです。磁気ループを使えば、回りの騒音、雑音に邪魔されずに、目的の声、音だけを正確に聞き取る事が出来ます。公共施設への設置は必要不可欠です。
ところが区内の公共施設には障害保健福祉センターのホール1ヶ所しか設置されていません。
聞きにくい声や音が、鮮明に聞こえれば外出や対話が楽しくなります。
難聴者や高齢者の社会参加を促すため、積極的に磁気ループ(専用受信機を含む)の導入を図るべきです。
1.福祉会館や、区民センター、各総合支所など、区施設に積極的に設置すべきです。
2.既に設置されている施設を区民に周知し、利用の促進を図るべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、難聴者への磁気ループの設置についてのお尋ねです。
まず、磁気ループを区施設に設置することについてです。現在、磁気ループは、障害保健福祉センターの多目的体育室に設置しておりますが、センターで保有している磁気ループに対応した受信用補聴器の貸し出し実績はありません。難聴者の方がこの設備を使用する際の効果や使いやすさなどを検証するとともに、難聴者とご家族の方、そして港区聴覚障害者協会からのご意見も参考に、設置について検討してまいります。
次に、設置施設の周知及び利用促進についてのお尋ねです。
障害保健福祉センターの磁気ループにつきましては、障害者週間記念事業などのイベントを実施する際に、チラシやパンフレットに磁気ループが設置されている旨を明記する等周知に努めてまいります。また、障害者の方へ配布している障害者のためのサービス一覧に掲載するとともに、港区聴覚障害者協会など関係団体へ改めて情報を提供し、利用の促進を図ってまいります。
7、孤独死をなくすために質問
区内の65歳以上の一人暮らしは、国勢調査によれば10,000人を超える状況になっています。
内閣府の調査によれば、一人暮らしの高齢者では、周囲との会話が電話やメールを含めて2~3日に1回以下という人が、女性32%、男性41%で社会的な孤立化が進んでいることが明らかです。また、「困ったときに頼れる人がいるかどうか」の調査では一人暮らしや、暮らし向きが苦しい人に「いない」という割合が大きくなっています。
高齢者の孤立化は孤独死にもつながります。昨年度区内で11件の孤独死がありました。死後推定10日後に発見された例もあります。尊い命の最後としてはあまりにも悲惨です。
区では、ひとり暮らし高齢者等への見守りを伴う事業として緊急通報システム、配食サービス、訪問電話、家事援助サービス、会食サービス、ごみの戸別訪問収集などを行っていますが、いずれの事業も利用者が200~800人余りと一人暮らし高齢者の1割にもなりません。
昨年世田谷区が行った高齢者実態調査でも、見守り訪問を「今後希望するかも」が7割になるなど高齢化への不安の実態があります。集合住宅の居住者の中には隣近所とのつきあいのわずらわしさを嫌う人も少なくありません。しかし、高齢化すれば他人を頼らざるを得なくなることから孤立化への不安も抱えていることを示しています。
孤独死を無くそうと先進的な取りくみをしている千葉県・常磐平団地では、一人暮らし世帯の安否を確認する見守り活動が行われています。
高齢者の社会的孤立を防ぎ、人生の最後まで高齢者の尊厳が保たれるよう支援が必要です。
①いつでも電話で話し相手になるホットラインを設置すること。
②空き店舗などを活用し、気楽に立ち寄れる「たまり場」をつくり、つながりづくりをすすめること。
③見守りを伴う事業の利用者を拡げるため、事業の周知徹底を図ること。
④見守り・声かけ活動を行っている港区社会福祉協議会など、地域ネットワークづくりへの支援を強化すること。
答弁を求めます。
【答弁】次に、孤独死の防止についてのお尋ねです。
まず、いつでも電話で話し相手になるホットラインの設置についてです。ひとり暮らし高齢者の孤独死を防止するためには、高齢者を孤立させない取り組みが必要です。区は、現在、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の方に週一回定期的に電話をし、お話しをするとともに各種相談もお受けする訪問電話事業を実施しております。また、地域包括支援センターでは、介護や健康、福祉、医療など高齢者にかかわるさまざまな相談をお受けしており、電話による相談は二十四時間受け付けておりますので、ホットラインの設置については考えておりません。
次に、気楽に立ち寄れる「たまり場」づくりについてのお尋ねです。
高齢者がふらっと気軽に立ち寄り、地域の人と交流できる場を、地域のさまざまな資源を生かして整備することは、高齢者の孤立を防ぐ有効な方法と考えております。今年度は、各総合支所で、地域特性を生かした芝の家などの交流の場づくりの事業を展開してまいります。来年四月に福祉会館から移行するいきいきプラザにおきましても、地域の高齢者が気楽に立ち寄り、さまざまな交流ができる施設運営に、より一層努めてまいります。
また、空き店舗を活用した交流の場づくりは、魅力ある商店街の育成にもつながります。交流の場の確保の一つとして、商店街とも協議しながら引き続き検討してまいります。
次に、見守りを伴う事業の周知徹底についてのお尋ねです。
高齢者の見守りを伴う事業といたしましては、緊急通報システム、配食サービス、訪問電話、家事援助サービス、会食サービス、ごみの戸別訪問収集事業などを実施しております。これらの事業につきましては、これまでも広報みなとへの特集記事の掲載、地域包括支援センターや総合支所等の窓口での事業案内の配布、介護事業者の研修会などで周知してまいりました。また、昨年度は、ひとり暮らし高齢者実態調査の対象者全員に、緊急通報システム、救急医療情報キット、災害時要援護者登録事業の案内を掲載したパンフレットを配布いたしました。今後は、これらに加え、ケーブルテレビでの事業の紹介、出前講座での説明など、より多くの区民の皆様に利用していただけるよう一層周知してまいります。
次に、地域ネットワークづくりへの支援を強化することについてのお尋ねです。
高齢者の見守り活動は、町会・自治会をはじめ地域のさまざまな活動主体との連携によるネットワークを構築することで、より実効性のある事業となります。区は、平成十九年十一月に民生委員・児童委員をはじめ、警察、消防、港区社会福祉協議会など地域のさまざまな活動主体を構成員とする港区高齢者地域支援連絡協議会を設置し、本年三月には、各総合支所ごとに地区高齢者支援連絡会を設置いたしました。今後、区といたしましては、町会・自治会の見守り活動や港区社会福祉協議会の見守り事業などの地域ネットワークづくりについて、連絡会を活用して情報の共有化や連携を図ることにより、一層支援してまいります。
8、旧国立保健医療科学院跡地の活用について
2008年7月、旧ともえ小学校跡地との交換用地として、旧国立保健医療科学院跡地の取得が議会に報告されました。
歴史的にも貴重な建物は、外観を生かし保存活用し、延べ床面積15,000平米のうち一部を在宅緩和ホスピス・ケアセンターとして活用、残りについては未定、これから区民の意見をきき決めていくというものです。
私たちは、活用方について今までにも提案していますが、特に不足している特別養護老人ホームなどの高齢者施設、保育園などの児童施設として活用すべきと考えます。
また、周辺との環境を考えれば、郷土資料館なども有効です。
区民に役立つ施設建設を早急に決定すべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、旧国立保健医療科学院跡地の活用についてのお尋ねです。
旧国立保健医療科学院の建物は、歴史的な風格や趣を備えており、保全を前提に、在宅緩和ケア支援を行う施設のほか、地域の方々が利用できる施設を整備する予定です。また、広い床面積を生かして、その他の施設の整備についても検討を進めております。本年の三月と四月に、六日間にわたり合計十二回開催した施設見学会には、約二百名の方々が参加し、アンケートでは活用を期待するさまざまな意見をいただきました。こうした区民の皆さんの高い関心を踏まえ、今後、建築基準法など関係法令への適合を検証しながら、活用に向けた検討を重ねてまいります。
9、子宮頸がんワクチンについて
日本では毎年15,000人の方が子宮頸がんになり、約3,500人が亡くなっています。なかでも20歳代、30歳代の子宮頸がんが増えています。
ワクチンを接種すれば、7割を予防できますが、費用が高額なため(3万円以上)経済的な事情で断念せざるを得ない方も出てきます。
23区でも既に杉並区、渋谷区で実施していますが、東京都は今年度から子宮頸がんワクチンの助成をはじめました。各自治体が実施した場合、ワクチン予防接種にかかる費用や、普及啓発、情報提供にかかる費用を都が半額助成する内容です。
有効性が認められたから東京都は助成に踏み切ったわけであり、「国の動向をみてから」などといっていては、救える命も救えなくなります。
港区でもすぐに実施すべきです。
答弁を求めます。
【答弁】 次に、子宮頸がんワクチンについてのお尋ねです。
現在の子宮頸がんワクチンにつきましては、有効性や効果の持続期間、追加接種の必要性、接種推奨年齢など、検討を要する課題が多くあります。また、子宮頸がんを完全に防止するためには、ワクチン接種とあわせて定期的な検診が不可欠とされております。区といたしましては、国の厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会における検討結果を踏まえ、ワクチン接種の公費負担の必要性について検討してまいります。
10、ヒブワクチンについて
細菌性髄膜炎の予防に有効なのがヒブワクチンです。
日本では年間約1,000人の子どもがかかり、約5パーセントが死亡、命が助かっても知的な障害や手足の麻痺などの後遺症が残る場合があります。
ヒブワクチンについても東京都は今年度から助成を開始、子育て中のお母さんたちに朗報をもたらしました。23区中すでに18区で実施というのに、港区は未実施です。
港区でも実施に踏み切るべきです。
答弁を求めます。
【答弁】 次に、ヒブワクチンについてのお尋ねです。
国は、ヒブワクチンの定期接種化の検討を始めており、ヒブワクチンの安全性や効果を確認するための調査を実施いたしました。平成二十二年三月にはデータの集計を終え、その結果を踏まえて、今後、方向性が出される予定です。区といたしましては、区民が安心して接種できることが最も重要と考えており、国の予防接種部会での評価を踏まえつつ、検討してまいります。
11、小児用肺炎球菌ワクチンについて
小児に重い症状をもたらす細菌性肺炎は、ワクチンで8割以上が防げるといわれています。日本では昨年10月に承認されたばかりですが、世界90カ国以上で承認され、発症率が大幅に減少しています。
東京都も助成に踏み切りました。港区でも実施すべきです。
答弁を求めます。
世界保健機構「WHO」もワクチンの定期予防接種を勧告しています。
効果の認められるワクチンは、国の施策として接種を進める態勢をつくるべきだと、国内の専門家も指摘しています。
重症化や死に至る危険もある子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの、法定接種を国に求めるべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、小児用肺炎球菌ワクチンについてのお尋ねです。
まず、小児用肺炎球菌ワクチン接種の助成についてです。小児用肺炎球菌ワクチンは、我が国では昨年十月十六日に承認され、本年二月二十四日から任意接種が開始されました。区といたしましては、区民が安心して接種できることが最も重要と考えており、国の予防接種部会の評価を踏まえつつ、検討してまいります。
次に、ワクチンの法定接種を国に求めることについてのお尋ねです。特別区保健所長会は、予防接種制度の見直しに向けた意見を取りまとめ、本年五月十七日に、全国保健所長会に提出いたしました。それを受けて、全国保健所長会は、任意予防接種の法定化について五月二十七日に、国に要望を提出しております。国では、予防接種部会において、予防接種制度の抜本的な見直しに向けて検討する方針と聞いており、今後もさまざまな機会をとらえて要望してまいります。
12、CTやMRI、脳ドックの検査費用の助成実施ついて
動脈瘤の破裂による死亡、脳内出血などによる死亡、死亡原因はいろいろありますが、定期的にCTスキャンやMRI、脳ドックなどでチェックすることで、大事に至る前に発見できる可能性が大きくなっています。
脳ドック(MRIによる検査)による早期発見の対象となる疾患は、脳腫瘍(のうしゅよう)や小さな脳梗塞(のうこうそく)などがありますが、特に未破裂動脈瘤が注目されています。動脈瘤が破裂して、クモ膜下出血を生じる確率についてはいまだに統一した見解は得られていませんが、早期発見による治療はきわめて重要です。
CTでは、頭蓋(ずがい)内の病変や、実質臓器の腫瘍など多くの疾患が外部から比較的容易に発見できるようになりました。
大相撲夏場所を脳梗塞で休場した岩木山が復帰を目指し病気とたたかっています。2月に手術した右ひじの経過を見るために撮ったMRI(磁気共鳴画像診断装置)画像から脳の血管の一部が非常に細くなっていることがわかりました。たまたまの検査で発見されました。いかに検査が大切かわかります。
MRIとCTとの組み合わせたNMR・CT検査もあり、医療技術の進歩によって、早期発見、早期治療により、多くの命が守られ、医療費の削減にもつながります。
区民の健康を守るために、節目節目の年齢でCTやMRI、脳ドックの検査を受ける費用の助成を行うべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、CTやMRI検査、脳ドック費用の助成についてのお尋ねです。
CTやMRI検査は、特定健康診査等の結果や自覚症状に応じ、保険診療により検査する場合が多く、その費用は医療保険で給付されます。また、脳ドックで未破裂動脈瘤などが早期発見された場合におきましても、その予防的治療法につきましては、安全性や長期的な有効性について、慎重な経過観察がなされている段階であり、現時点で、CT、MRI検査、脳ドック費用の助成は考えておりません。
13、特定不妊治療費助成に関する質問
日本で不任に悩むカップルは、7~10組に1組といわれ 、治療を受けている人は50万人ともいわれています。
日本共産党は、これまでも国の特定不妊治療費助成の増額と所得制限の緩和、保険が適応されていない治療への保険適応を求めてきました。
不妊治療には、経済的な負担のほか、精神的な苦痛も大きく仕事との関係でも様々な障害があり患者さんは大変な思いをしています。経済的な負担を取り除くことは最低限必要です。港区でも特定不妊治療費の助成を受けている方は、2007年度170件、2008年度266件、昨年度337件と増えています。
不妊体験者の自助グループ(NPO法人)が行った調査では、不妊治療に支払った治療費の総額が100万円以上になる人が47%にもなります。アンケートには、「働かないと治療費は払えないけど、治療と仕事は両立できない」といった声が多数寄せられています。こうした結果を基に、NPO団体は①特定不妊治療費助成事業の補助金の増額と、条件の見直し、②不妊治療の保険適応範囲の拡大を求める署名に取り組み、国会に提出しています。
東京都の助成制度と港区の助成制度との併給が可能ですが、東京都の場合は所得制限(夫婦合算で730万円)があるため、助成を受けられない方が多くいます。
①所得制限の撤廃と1回15万円、年2回、通算5年までといった金額や回数の撤廃を行うよう東京都に求めること。
②港区として、改善されるまでの間、所得制限によって東京都の助成制度の対象になっていない方について、東京都の助成額の上限30万円について支援をすること。
答弁を求めます。
【答弁】次に、特定不妊治療費助成についてのお尋ねです。
まず、制限の撤廃を東京都に求めることについてです。東京都の助成内容は、国の制度に準じて、所得、支給回数、支給年数などの制限を設けております。国は平成二十一年四月から助成金額と所得制限の上限額の引き上げを行い、東京都もそれに準じて制度を見直しました。これにより、助成金額を一回十万円から十五万円に、所得制限額を年間六百八十万円から七百三十万円に引き上げました。このように国や東京都が助成内容をレベルアップしたことから、区といたしましては、制限の撤廃を東京都に求めることは考えておりません。
次に、区としての特定不妊治療費の助成についてのお尋ねです。
区は、独自事業として特定不妊治療費助成事業を実施しております。この事業は、所得制限を設けず、助成金額も二十三区中、最も高い水準となっています。したがいまして、所得制限のため東京都の事業の対象とならない方に、東京都の助成金額を上乗せして支給することは考えておりません。
14、地上デジタル化について
テレビ放送が地上デジタルに完全移行する2011年7月24日まで、あと400日となりました。
地デジ受信機の普及や、都市部のビル陰に対応する共聴施設の改修の遅れが大きな課題となっています。
地デジ化が進まない理由は①費用が高額で、個人負担が大きいということです。全国消費者協会の調査によれば、対応済みの人が「地デジ対応にかけた費用」は10万円~50万円 が69.8%、平均額は約27万円です。
また、②経済的に厳しい世帯の遅れです。総務省が3月に実施した「地上デジタル放送に関する浸透度調査」によれば地デジ対応受信機の普及率は、年収200万円以上は8割を超えている一方、200万円未満は67.5%と差が大きく、経済的に厳しい世帯への支援が課題となっています。
さらに、③共聴施設のデジタル化対応の遅れがあります。3月末現在、ビル陰など受信障害対策の対応済率が47.8%で期限までの100%達成はほぼ不可能な状況です。
ところが、総務省や放送事業者でつくる「全国地上デジタル放送推進協議会」が発表した「アナログ放送終了計画」によると、今年7月からテレビ画面の上下に黒い枠(レターボックス)が、すべての番組に入る。現在は右上にアナログの小さな文字だけですが、来年1月からは「ご覧のチャンネルは7月で終了します」と「お知らせ」の字幕まで付ける。さらに、7月1日からは画面いっぱいの「お知らせ」画面と音声だけにするという「脅し」そのものです。
「テレビ難民」を生まないために
①画面表示の計画を止め、地デジ受信機の普及に応じてアナログ放送停止計画の延期を国に求めること。
②共同アンテナの地デジ化を促進するため共聴施設の調査、改修、撤去費用を負担するよう国に求めること。
答弁を求めます。
【答弁】次に、地上デジタル化についてのお尋ねです。
まず、地上デジタル化の延期を国に求めることについてです。平成二十三年七月からの地上デジタル放送への全面移行について、国は、放送事業者などと連携して、積極的に広報に努めております。また、昨年十二月に公表されたデジタル放送推進のための行動計画では、各地方公共団体をはじめ関係機関の普及率向上に向けた具体的な取り組みが明示されております。区は、現在も機会あるごとに総務省テレビ受信者センターに対し、区民への丁寧な対応を要請しており、イベントや町会での相談会などを開催しております。今後も、地上デジタル放送への移行が円滑に進むよう、国の動向を注視してまいります。
次に、共聴施設の調査、改修、撤去費用の負担を国に求めることについてのお尋ねです。
国は、受信障害対策共聴施設のデジタル化対応に向け、個別アンテナ受信可否調査、助成金制度、法律家相談などの支援メニューに加え、デジタル化方策の検討、当事者間協議支援などの総合コンサルティング事業を五月から実施しております。また、国の制度として、集合住宅共聴施設への改修費用の助成金制度のほか、総務省関東総合通信局管内では、集合住宅に対し、無料の受信確認調査を実施しております。区といたしましては、こうした国の制度等の周知を図るとともに、デジタル化の対応状況を注意深く見守ってまいります。
15、品川駅東西自由通路の安全確保について
品川駅港南口側は、大規模なビルやマンションの建設によって乗降客が急増しています。品川駅の2008年度の乗車人員は、JR東日本が328,439人、JR東海が23,800人、さらに京浜急行の乗降客が251,393人 です。JR東日本では6番目に乗車人員の多い駅となっています。
朝の通勤時間帯は洪水のような人波が押しよせ、乗車のため改札に向かう人は、毎朝洪水を渡りきって両端の通路を身を縮めるようにしての通行となり、身の危険すら感じる状況です。現在、駅前に新たなビル建設が進み、芝浦水再生センター再構築に伴う巨大ビル建設の計画もあり、さらに駅利用者の増加が懸念されます。私たちはこれまでも安全対策を求めてきましたが、以前配置されていた誘導員がいなくなるなど対策が逆行しています。
区民の安全を確保するため、安心して通行できる対策をとるようJRに対して要求すべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、品川駅東西自由通路の安全確保についてのお尋ねです。
品川駅東西自由通路につきましては、駅周辺のまちづくりの動向を見据え、混雑緩和など安全で安心な歩行空間の確保が必要であると考えております。引き続き、JR東日本などの鉄道事業者に対して、歩行者の安全確保を要請してまいります。また、平成十九年十一月に東京都が策定した、品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドラインも踏まえ、東京都及び鉄道事業者等との協議を積極的に進め、安全確保に努めてまいります。
16、家賃助成制度の復活・拡充について
港区の家賃は他区と比べても高く、物価も周辺区よりも高くなっています。港区に住めない状況です。港区はマンション化が進み、安い家賃の住宅が次々と姿を消しています。住宅相談も多数寄せられますが、都営住宅の申し込み倍率は、この間では百倍前後となっており、ごく一部の方しか入居できません。
区内に長年住んでいる世帯で、子どもさんが結婚し、出産・子育てになると、スペースの条件があり、同居できなくなります。区内に住まいを探そうと思っても、都営住宅は先ほど述べたとおりの倍率で入れず、民間の2LDKのマンションでも18万円から25万円くらい賃料がかかり、到底借りることもできず、近県のマンションに引越されたという実例も多くあります。3LDKで15万円だそうです。
長年住んでいた港区から、出産を機に転出せざるを得ないなど、あってはならないことです。
私たちは、この間、こうした実態も示し家賃助成制度の復活・充実を要求してきましたが、区は、①定住人口が順調に回復している。②平成13年に家賃助成を受けた世帯の動向調査を実施したが、23%が区外へ転出している。効果は時限的。・・・という理由で制度の復活は考えていないという態度です。
以前にあった助成制度は、5年間の時限的な制度で、期間が来れば終わってしまいます。だから、助成期間終了により区内に住めなくなり転出していったのです。時限的だったことが、効果が出なかった原因です。助成制度を恒常的とすれば大きな効果が出てくるのです。
渋谷区では助成制度を復活、文京区ではバリアフリー化と組み合わせ助成制度を実施するといいます。
港区でも助成制度の復活・充実をすべきです。答弁を求めます。
さらに、当面、生活保護基準の1.2倍以下の収入で、民間賃貸住宅に居住している世帯へ家賃の一部を助成すべきです。単身世帯月1万円、二人以上世帯月2万円の支援策を実施すべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、家賃助成制度についてのお尋ねです。
まず、助成制度の復活及び充実についてです。区の人口が昨年、四半世紀ぶりに二十万人を超えるなど、定住人口の回復が着実に進んでいることから、家賃助成制度の復活、拡充は考えておりません。区では子育て世代に加え、高齢者世帯等に対して、区立住宅において当選倍率の優遇措置を実施するなど、住宅の確保に配慮が必要な方々に対する支援を行っております。
次に、民間賃貸住宅に居住している低所得世帯への助成についてのお尋ねです。
区では、低所得世帯に対する支援として、区営住宅が真に住宅に困窮する低所得者に対して公平・的確に供給されるよう取り組むとともに、老朽化した区営住宅の建て替えの検討を行っているところです。したがいまして、民間賃貸住宅に居住している方々に対する家賃助成は考えておりません。
17、ちぃばすの改善について
3月24日の運行が決まった以降、私たちのところに、「買物に行く元気が出た」、「お風呂に行くのが楽しみ」、ちぃばすで「港区を一周してみたい」など、多くの歓迎の声が寄せられています。
その一方、反対側のバス停がないので「買物をした帰りが大変」、「先に行きたいのに終点だからと降ろされてしまい、200円かかる」、「ここにもバス停が必要」、「ちょっとした椅子があると助かる」、台場をはじめ多くのところから「なぜ、私たちのところは走らないのか」など、様々な改善、要望も寄せられています。
運行開始日に間に合わせるため、問題点を抱えたままのスタートとなりました。この間区民から寄せられている問題点については、できるところから改善の手立てを尽くす必要があります。
詳細な改善点については、交通環境等対策特別委員会での決まりにしたがって、文書で提出します。それに基づいての対応をお願いしておきます。
ここでは、改善すべき基本について提案します。①本来あるべき反対側のバス停の設置。②バス停の位置の改善、新設。③終点でおろされてしまう問題(降ろされる。200円かかる)、④他系統への乗り継ぎ問題、⑤乗り継ぎ乗車の場合の軽減策や回数券の発行、早急にこれらについて改善に取り組むべきです。その際、人手が足りないのであれば、臨時に体制強化を図って取り組むべきです。
答弁を求めます。
【答弁】最後に、「ちぃばす」の改善についてのお尋ねです。
「ちぃばす」の新規五路線の実証運行を本年三月に開始してから、バス停留所の新設や麻布ルートが循環ルートのため、終点で一度降車し、再度乗車する場合は追加料金が必要となること、また、他のルートへの乗り継ぎ方法やバスの遅延解消などについて等、利用者の皆さんからさまざまなご要望をいただいております。これらの要望への対応も含めて、コミュニティバス事業の課題の解決につきましては、昨年三月に策定した港区地域交通サービス実施計画に基づき、港区地域公共交通会議で取り組むこととしております。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
18、学校図書館について
最初は、学校図書館司書の配置についてです。
学校図書館は、学校教育に欠かすことのできないものとして、法律により、すべての学校に設置されています。「学校教育の中核」ともいわれます。
なぜかといえば、物語や小説、学習教材でも、書かれたものを読みこなす力、読解力は、どんな教科にも欠かせない力です。読む習慣がある子は、国語だけでなく、算数・数学でも力をつけることができます。
読書は、豊かな情操、健全な教養もはぐくみます。
学校図書館の役割を整理すると、ひとつは「読書センター」です。読みたい本、必要な本があり、読書を楽しめる場所ということです。学校教育の一環として読書指導をする場所でもあります。
もうひとつは、「学習・情報センター」としての役割です。「学び方を学ぶ場」ともいわれています。本や資料を使った調べ学習に使われることが多く、授業で学んだことを自分で深めるのにも活用されます。学校図書館は学習の質を改善します。 昼休みや放課後の「子どもたちの居場所」としての役割も期待されています。
わが党区議団の提案によって、学校図書館にリーディングアドバイザリースタッフが配置され、学校図書館が見違えるようになり、カギのかかった図書館から児童・生徒に利用される図書館にかわりました。これ自体は大変に喜ばしいことです。
しかし、リーディングアドバイザリースタッフは、非常勤であり、司書資格のない人もいます。その上、報酬も低く、個人のボランティア精神に負うところが大です。
真に児童・生徒のための学校図書館とするために、司書資格をもった人の配置、常勤化が必要です。
当面、リーディングアドバイザリースタッフの全日配置、報酬の引上げを図るべきです。
答弁を求めます。
【教育長答弁】ただいまの共産党議員団を代表しての沖島えみ子議員のご質問に順次お答えいたします。
学校図書館についてのお尋ねです。
まず、学校図書館司書の設置についてです。平成二十一年度の全国学力・学習状況調査によると、一日当たり一時間以上読書する港区の児童・生徒の割合は、小学校六年生で約二四%、中学校三年生で約一八%であり、東京都や全国と比べ、いずれも五ポイントから八ポイント高い値を示しております。このことは、各学校における読書指導計画に基づくリーディングアドバイザリースタッフを活用した各学校の指導の成果であるととらえることができます。今後、有償ボランティアであるリーディングアドバイザリースタッフの配置日数及び報償費の引き上げについては、各小・中学校における読書指導の成果や今後のあり方を検討する中で、検討を進めてまいります。
19、蔵書の充実について
私たちの提案で学校図書館の予算が増え、蔵書が増え、図書館の環境も改善されてきました。しかし、文部科学省が決めた学校図書館図書標準を下回る学校があります。
2010年3月31日現在、2つの小学校が図書標準から不足しています。今年度、不足図書充足分の予算をつけましたが、一冊当たりわずか500円です。学校図書館にふさわしい本が購入できるとは思えません。また、古くなった図書を廃棄して、新規購入も必要ですから、それにふさわしい予算をつけるべきです。
それぞれ答弁を求めます。
【答弁】最後に、蔵書の充実についてのお尋ねです。
学校図書予算につきましては、学級数や在籍者数に応じて各学校に配当しており、また、学校図書標準に達していない学校には、不足分を上乗せして充実を図っております。学校図書標準に満たない小学校二校は、今年度中に図書標準を達成する予定であり、今後ともさらなる蔵書の充実に努めてまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
2010年区議会第二回定例会での質問
2010年6月10日質問者 星野たかし 議員
1.核兵器廃絶、基地のない日本、港区を実現させることについて
2.米軍普天間基地の無条件撤去、米軍麻布ヘリポート基地早期返還ついて
3.生活保護行政の改善について
4.「無料低額宿泊所」について
5.市街地再開発事業の検証実施について
6.白金6丁目の高層ビル建設について
7.公共施設のバリアフリー対策について
2010年第2回定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として区長、議長に質問します。
1、核兵器廃絶、基地のない日本、港区を実現させることについて
最初は核兵器廃絶、基地のない日本、港区を実現させることについてです。
はじめに核兵器廃絶の実現について質問します。
5月3日から国連で開かれていた2010年核不拡散条約(NPT)再検討会議は5月28日、全会一致で最終文書を採択し閉幕しました。
最終文書は、「すべての国が核兵器のない世界を達成し、維持するために必要な枠組みを確立するための、特別な取り組みを行う必要性について確認する」と明記しました。核保有国に核兵器廃絶への「いっそうの取り組み」「具体的な進展」を求めることが確認されたことは、「核兵器のない世界」にむけて重要な一歩前進です。
こういう前進ができたのは、世界各国の人たちの、核兵器廃絶の運動と、とりわけ運動の先頭に立ってきた被爆者の方々、原水爆禁止世界大会を続けてきた、日本原水爆禁止日本協議会などの長年の運動の結果です。
日本共産党は、志位委員長を団長とする訪米団を送り、(1)「核兵器の完全廃絶を実現するという核兵器国の明確な約束を再確認する」こと、(2)「核兵器廃絶のための国際交渉を開始する合意をつくる」という二つの要請を、カバクチュラン再検討会議議長をはじめ会議主催者、国連関係者、各国代表団におこない、可能な最大限の力をつくしました。
NGOとともに、わが党がすすめた活動は、NPT再検討会議が、重要な一歩前進の結論への貢献となったと思います。
港区からも4人の代表団が参加した約1500人の日本原水協代表団は(日本からは総勢2000人が参加)、現地ニューヨークで宣伝・署名活動、大パレードなど行い、日本からの690万人余の署名を再検討会議に手渡しました。
カバクチュラン再検討会議議長は、5月3日の再検討会議の開会にあたり「昨日私は、市民社会が集めた署名を受け取りました。彼等の熱意はたいへん大きなものがあります。私たちは、この熱意に答えなければなりません。」と演説しました。
わが党は、日本と世界の反核平和運動と共同し、「核兵器のない世界」にむけ、核兵器廃絶交渉のための国際交渉をすみやかに開始することを、ひきつづき強く求めていくものです。
港区は、わが党の提案もあり4月1日に、平和市長会議に加盟しました。
市長会議は、自らが策定した「2020年までに各国政府が遵守すべき核兵器廃絶の道筋」を示した「ヒロシマ・ナガサキ議定書」の、NPT再検討会議での採択へ向けた運動をすすめてきました。 区長はこの議定書に賛同し「全ての国家が同議定書を遅滞なく採択し、核兵器廃絶に向け、誠実に取り組むことを求めます」と都市アピール署名も行ないました。再検討会議で、国際社会が確認した成果のうえにたち、核兵器の廃絶を訴える、平和都市宣言を行なっている自治体として、港区が更に核兵器廃絶への取り組みを強めていくことが求められているのではないでしょうか。
そのために、
1、NPT再検討会議への平和市長会議と港区の取り組みを区広報紙、港平和展などを通じ、広く区民に知らせ、区民の協力を得ること。
2、平和市長会議の要請に応え、他自治体に平和市長会議への加盟要請を積極的に行うなど、市長会議の取り組みに協力すること。
3、核廃絶への各国協議の実現と、早期の実施を、この機をとらえ、他自治体とも連携しながら、更に要請を強めること。
答弁を求めます。
【答弁】ただいまの共産党議員団の星野喬議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、核兵器廃絶の実現についてのお尋ねです。
まず、NPT再検討会議への平和市長会議の取り組みに関する周知についてです。区は、本年四月、港区平和都市宣言の理念に基づき、世界の都市が核廃絶に向けて連携する平和市長会議に加盟いたしました。核不拡散条約の運用と履行を検討するNPT再検討会議が本年五月に開催されましたが、平和市長会議は代表団を送り、さまざまなアピールを行っております。このNPT再検討会議に対する平和市長会議と港区の取り組みにつきまして、広報紙や平和展等を通じ、広く区民に紹介してまいります。
次に、平和市長会議の取り組みへの区の協力についてのお尋ねです。
平和市長会議における核廃絶を目指す取り組みにつきましては、機会をとらえ、区として協力してまいります。
次に、核廃絶に対する各国協議の実現等への区の取り組みについてのお尋ねです。
区といたしましては、国際社会における核廃絶に向けた動向を注視しつつ、加盟している平和市長会議の活動を通して、他の自治体と連携しながら、取り組んでまいります。
2、米軍普天間基地の無条件撤去、米軍麻布ヘリポート基地早期返還ついて
日米両国政府は、5月28日、世界一危険な普天間基地の移転先を、名護市辺野古にすること、鹿児島県徳之島や日本本土にも、訓練の移転を行なうと明記した共同発表を行いました。これは「国外、県外」という自らの公約を裏切り、4月25日の沖縄県民大会に示された「県内移設」絶対反対という県民の総意、徳之島島民の6割が参加した「訓練移転反対」の意思を踏みにじるもので、断じて許せません。
日本共産党は、この方針の中止を強く求めるものです。
日本共産党は、志位委員長が5月7日、米国政府に対し、普天間基地は「無条件撤去しかない」、「(国内に)受け入れ先はない」との、沖縄県民・国民の意思、徳之島をはじめとする、移転が取り沙汰される現地の声をしっかりと伝え、「無条件撤去」の決断を迫りました。
党首をすげ替えた、民主党政権がいまやるべきことは、米国が「地元の合意が必要」といっているのですから、「普天間基地の無条件撤去」が国民、県民の声であることを米国政府にしっかりと伝え、「無条件撤去」を要求すべきです。
23区唯一米軍基地を抱える自治体港区として、「普天間基地の無条件撤去」という沖縄県民、国民の民意を米国政府にしっかりと伝えるよう、政府に要求すべきです。
答弁を求めます。
また、米軍ヘリポート基地の早期返還実現も、基地被害をなくし、平和な港区、安全な生活を願う港区民の強い声です。
区民、議会、港区が協働して引き続き米政府、国に対し強く返還を求めるべきです。
区長、議長の答弁を求めます。
【答弁】次に、米軍普天間基地の無条件撤去についてのお尋ねです。
普天間基地問題については、国の責任で解決すべきものであり、国へ要請することは考えておりません。
次に、米軍ヘリポート基地の早期返還についてのお尋ねです。
区と区議会は、これまで、区民の安全で安心な生活を守るため、米軍ヘリポート基地の早期撤去を目指し、関係機関への要請などに取り組んでまいりました。今後も、区議会の皆様と相談しながら、東京都とも連携して、取り組みを進めてまいります。
3、生活保護行政の改善について
次に生活保護行政の改善について質問します。
この間、生活保護行政の実態について指摘し、改善を求めてきました。生活保護行政はこうあるべきという区の対応がありました。
ある若者の母親が死亡、それと同時に住居がなくなり、派遣の旅がはじまりました。大阪からはじまった派遣、最後は仙台で派遣切りにあい、自治体に相談しながら、乗り継ぎ、乗り継ぎでなんとか港区にたどり着きました。なにかあったら「共産党に相談した方が良い」との知人の言葉を思い出し、私たちのところに飛び込んできました。この方は、鹿児島の友人が「仕事を含めて面倒みる」と言ってくれているとのことで、鹿児島に帰りたいとの相談でした。
生活保護担当に相談したところ、鹿児島までのキップ...現物支給するとのことで、本人は友人のところに身を寄せることができました。担当部署の知恵と努力と決断に敬意を表したいと思います。
厚生労働省の調査で、生活保護基準の最低生活費を下回る世帯が705万世帯にのぼり、そのうち、生活保護の受給は108万世帯(15.3%)しかないことが判明しました。
現行の生活保護は受給要件が厳しく、所得が最低生活を下回っても、貯蓄が最低生活の1カ月分未満でないと受けられません。この要件を満たす世帯でも保護を受けているのは32.1%にとどまります。
また、総世帯に占める生活保護基準未満の所得の世帯(保護受給世帯を含む)の割合は14.7%にのぼります。
この計算では、最低生活費に家賃分や医療・介護費などが含まれていません。これらを含めれば最低生活費が上がり、それに満たない所得の世帯数はさらに増えます。低所得世帯に対する保護受給世帯の割合はいっそう低下することになります。
この調査結果で明らかなように、本当は生活保護が受けられる方が切り捨てられているのが実態です。相談窓口で追返えすなど、全国各地で問題になっている水際作戦です。
港区でもあいかわらず相談者の人間性を否定するような対応が行われています。
Aさんからは、「年金を担保に金を借りれば良いと言われ借りてしまった。自己破産を申告してます。助けて下さい」と相談がありました。「年金を担保に借金しろ」などと言うことを、区民生活を守る立場にある行政が絶対にやってはならないことです。
Bさんは、こどもが大学の二部に行きたいと言ったら、「そんなの大学ではない。一日8時間働いたらどうだ。」と言われ、強いショックを受けたとの訴えです。
Cさんは、いろいろな事情でホームレスになり、生活保護の窓口にいったが、申請書もくれず相手にされなかった。「倒れたら救急車で運ばれ退院したらまた戻るという繰り返しかないとあきらめた」と、ホームレスをしていました。
二度とこういう訴えが、寄せられることがないよう、憲法、生活保護法に基いて、人間味あふれる対応をすべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、生活保護行政の改善についてのお尋ねです。
生活保護制度は、憲法第二十五条に定める国民の生存権保障を具体化したものであり、生活に困窮した際の最後のよりどころとなるものです。区では、相談窓口での対応にあたっては、相談者の置かれている状況に思いをいたしながら、丁寧できめ細かな支援を行っております。今後も、生活保護制度の重要性を常に認識し、要件を満たし、かつ、生活保護の受給を求める方が保護を受けられないことがないよう、適切な生活保護の適用に努めてまいります。
4、「無料低額宿泊所」について
生活保護費の大半をピンハネし、元路上生活者を劣悪な環境の相部屋に入れる一部の悪質な「無料低額宿泊所」などの「貧困ビジネス」が横行しています。こうした背景に、福祉事務所が被保護者をそこに追い込むような、保護費の自治体負担の独特な仕組みがあることが、しんぶん「赤旗」が入手した東京都の内部文書などで分かりました。 生活保護法では保護費の4分の3を国が、4分の1が地元自治体が、それぞれ負担することになっています。
東京都の自治体の場合、一般的には、23区や市が自治体負担分の全額を負担。東京都は、それ以外の町村と島しょ部の自治体分を持ってきました。 ところが、東京都の内部文書(通達)によると、路上生活をしてきた人など、住所がない人が、新しく生活保護を受けた場合、都内のどこで申請しても、自治体負担分を全額、東京都が持つとしています。ドヤなどの旅館に入居した場合は最長3カ月まで都が負担し、「無料低額宿泊所」の場合は、期限がありません。
「無料低額宿泊所」の場合、ほとんどが相部屋で、食事は一日2回、お風呂も週3回で、月84,800円~9万円程度です。生活保護の場合、手元に2~3万円しか残らないことになります。
港区で生活保護を受給した25人の方が「無料低額宿泊所」に入居しています。本来であれば区内のアパートなどを借りて、自立した生活を支援すべきです。
現在、「無料低額宿泊所」に入居している人の意思を確認しながら、自立した生活ができるよう、懇切・丁寧な相談、助言を行うべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、「無料低額宿泊所」についてのお尋ねです。
生活保護の開始時に安定した住居のない生活困窮者に対しては、東京都と特別区二十三区が共同で設置している緊急一時保護センターなどの施設を活用するほか、社会福祉法に規定する「無料低額宿泊所」も緊急的に利用しながら、増加する生活相談に対応しております。「無料低額宿泊所」の利用につきましては、経過的な利用であることに十分留意し、利用が長期間とならないよう、利用者のその後の生活状況や今後の希望等を個別に把握していきます。自立した生活が可能な方に対しては、アパート等一般居宅への移行を図り、居宅での生活が困難な方に対しては、保護施設や老人ホームへの入所手続きを進めるなど、今後とも適切に対応にしてまいります。
5、市街地再開発事業の検証実施について
4月15日に行われた港区都市計画審議会の中で、保健衛生分野の学識経験者委員から、「この間区内で行われてきた再開発について、どういう問題がおこっているのか、検証委員会をつくって検証するべきだ」という主旨の提案がありました。街づくり支援部長は、「何ができるか、検討させて頂きたい」と検討を約束しました。
私たちは、再開発事業によって、長年住んできた方が転出を余儀なくされてきたこと、風害、日影、電波障害、交通渋滞、大気汚染、温室効果ガス排出などの環境破壊、大規模地震時の安全性が確保できないこと、地域コミュニティーの破壊、等々を示し、再開発を推進する区の姿勢を改めるよう求めてきました。
1、都計審で提起された再開発事業の検証を具体的に実行すること。
2、検証にあたっては、従前の住民・地権者の動態、環境への影響、災害時の安全、コミュニティー等々を正確に検証すること、また、区民が再開発事業、超高層ビル建設の是非をどのように考えているかなども調査・検証すること。
答弁を求めます。
【答弁】次に、市街地再開発事業の検証実施についてのお尋ねです。
市街地再開発事業は、環境などへの配慮をした上で、災害に強い街づくりのため、地域に貢献する道路、緑地などの公共・公益施設の整備や住宅の確保、さらには商業、業務、文化などの各機能が調和した、将来にわたり安全・安心なまちを実現する、高い公共性を備えたまちづくりの手法です。このようなまちづくりを推進するために、区は、事業の規模を問わず、事業内容などを適切に評価した上で、市街地再開発事業を支援しております。これまでも区は、都市機能の更新状況や事業効果、都市計画の目標の実現状況等を確認し、まちづくりの成果をその後に実施される事業への指導・支援の中に生かしております。今後、こうして積み重ねてきた経験をもとに、市街地再開発事業を評価検証する仕組みについて検討を深めてまいります。検証すべき事項、調査内容につきましても、その中で検討してまいります。
6、白金6丁目の高層ビル建設について
建設予定地周辺は、ほぼ9割が2階から3階の戸建て住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地です。この地は戦後に東京都が戸建ての都営住宅を建て、後にこれが払い下げになり、大部分の住民は、住宅を親から引き継いで、この街並みに愛着を持ち60年以上住み続けてきています。
ここに、天空率を採用した、高さ約40メートルのマンション建設計画が昨年5月、近隣住民に知らされました。住民は寝耳に水で、平地に突出した建設計画に大変とまどいました。
当初、事業者は「マンションが建つことで環境が良くなって近隣の資産価値は上がる」などと根拠も示さず説明し、「法の範囲での計画、とやかく言われることはない」などと口にし、住民の批判を浴びていました。住民は住環境に著しく悪影響を与えると、約1年間にわたり計画変更を求めて、地域ぐるみで運動をすすめています。この間、住民から区議会に出された請願は全会一致で採択されています。
住民は一貫して建て主側の誠意ある説明、対応を求めてきました。しかし、建築主側は、住民が「社長はホームページで、まちづくりは住民との合意の基にと言っている」と問いつめると、「やれないものはやれない」と開き直り、風害の心配に対しては、「風害が起きることはない」といいきり、住民が「それなら」と計画地への風力計の設置を求めると「社の方針で取り付けない」と突っぱねます。これでは話しになりません。
この間、区役所での話し合いが行なわれましたが、その後の説明会も、住民が理解し納得できる内容ではありませんでした。住民から「説明会の回数かせぎだ」と指摘されるほどでした。しかし、建て主側は、「タイムリミット」と工事説明会、着工などの日程文書を住民に一方的に配り、工事説明会が行なわれなかったにもかかわらず、「スケジュール通り」着工すると通告しました。住民は当然に反発し態度を硬化させています。
区はわが党の質問に当然のことながら、「建築説明会はわかりやすく丁寧に行い、住民の理解を得るよう、工事を行なう際には必ず工事説明会の開催を」と紛争予防条例の主旨に沿った、事業主のとるべき態度を示しています。このまま着工となれば、紛争は明らかに拡大します。
区は事業主に対し、周辺環境への配慮と、適切で十分な説明を行い、理解を得、円満な話し合いがすすむよう、紛争予防条例に沿って指導し、それまで着工は行なわないよう厳重に指導すべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、白金六丁目の高層ビル建設についてのお尋ねです。
区は、建築に伴う紛争を予防し、生じた紛争を迅速・適正に調整するため、いわゆる紛争予防条例に、当事者等の責務を定めております。条例では、建築主は、周辺の生活環境への十分な配慮と、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならないとしております。ご指摘の建設計画につきましても、現在、住民の方々からの相談、要望を受け、条例に基づき、区が話し合いの場を設定しております。今後も、条例に基づき、誠意ある話し合いを重ね、住民の理解を得た上で工事に着手するよう、引き続き建築主を指導してまいります。
7、公共施設のバリアフリー対策について
最後に公共施設のバリアフリー対策について質問します。
はじめに地下鉄のバリアフリー化推進についてです。
鉄道など公共交通機関のバリアフリー化の推進は法律でも定められ、この間一定推進されてきました。現在、区内の駅でエレベーターもエスカレーターも未整備の駅は、東京メトロの青山一丁目駅、芝公園駅と広尾駅の3駅です。このうち青山一丁目駅は一部整備が決まり、芝公園駅は現在エレペーター設置工事が進んでいます。残るは広尾駅のみになりました。
同駅は港区と渋谷区にまたがり出入り口が設置され、港・渋谷区民をはじめ通勤者、都立中央図書館、有栖川公園などの公共施設利用者など、1日当り5万6千人もの乗降客があります。特に周辺には南麻布、広尾の都営住宅、都立広尾病院、日赤医療センター、特別養護老人ホーム麻布慶福苑・ありすの杜・ベルなどがあり、施設への来訪者を含め高齢者や障害者など移動に困難な方々や患者さんの利用も多く、利用者にとっては大変利用しづらい駅となっています。また、ベビーカーの利用者からも改善が強く求められています。
5月28日、港区、渋谷区在住の利用者方々が、東京地下鉄株式会社(東京メトロ)本社にエレベーター設置を求める要望書を提出し早急な改善を求めました。利用者は「メトロは3年前、設置の方向が出てきたと言っていた。もう待てない」、障害のある方は「定年まで20数年広尾から国立まで通っていていた。まだ若かったときでも階段は3回以上休まないとならなかった。今は広尾駅は避けてタクシーでJR恵比寿まで行っている」、子育て中の住民からも「ベビーカーに子どもを乗せたまま階段を上り下りする状態で大変危険」とエレベーター設置を求めました。
対応した東京メトロは、「利用者から広尾駅改善の声が多く届いている。」と言いながら、明確な対応策を示しません。
東京メトロに対し区として改善の早急な具体化を強く求めると同時に、改善にあたっては計画当初から利用者、住民との話し合いなどを開き、関係団体との協議も行い、利用者の要望が反映されるよう求めるべきです。
答弁を求めます。
広尾駅については、このほかにも、通路・ホームが狭い、階段が歩きにくいという声も聞かれます。事故があってからでは間に合いません。併せて改善を求めるべきです。
答弁を求めます。
また、青山一丁目駅は、浅草方面行きにしかエレベーターが整備されず、通路でも結ばれていません。このような駅はバリアフリー未整備駅として位置づけられています。青山一丁目駅についても東京メトロに早期解決を求めるべきです。
答弁を求めます。
次は道路交差点バリアフリー対策についてです。
天現寺交差点については、これまでも機会ある毎に質問してきました。横断歩道がなく、車椅子、ベビーカーを利用する人や障害のある人など、歩道橋利用が困難な方々は、すぐ目の前にある広尾病院に行くのに長時間かけて遠回りしたり、タクシーを利用しています。地域の方は「いつまで待ったら安心して生活ができるのか」と早期改善の声を募らせています。エレベーター設置、歩道整備のための車道中央部への十分な安全地帯設置、歩道橋へのエレベーター設置のための歩道の拡幅など、あらゆる可能性を更に追求し、車優先より市民生活優先の立場で、引き続き関係機関への働きかけを強化すべきです。
答弁を求めます。
最後に八千代橋交差点について質問します。
芝浦の八千代橋交差点はかって横断歩道がなく、障害者、高齢者、子育て世代の方々から、「歩道橋は利用できない。すぐ目の前に行きたいのに遠回りは大変。」と、永年にわたって改善を切に求めています。最近、旧海岸通りに横断歩道が設置されましたが、住民の方々が求めていたのは札の辻側の車道への設置でした。最近も、自転車で横断中の区民が、車にはねられそうになり危機一髪でした。緊急課題としても、住民が強く求めている場所への横断歩道設置を関係機関に求めるべきです。
答弁を求めます。
以上で質問を終わります。ご静聴有り難うございました。
【答弁】次に、公共施設のバリアフリー対策についてのお尋ねです。
まず、地下鉄のバリアフリー化推進についてです。地下鉄駅のバリアフリー化につきましては、これまでも機会をとらえて、鉄道事業者に対して要請してまいりました。ご指摘の広尾駅のバリアフリー化につきましては、区有地を活用する方向で調整を図っております。また、青山一丁目駅の銀座線渋谷方面ホームにつきましては、駅舎の構造上の物理的制約等により、バリアフリー化が困難な状況にあると聞いております。引き続き、利用者の要望を反映する取り組みを含め、鉄道事業者に対して要請してまいります。
最後に、道路交差点のバリアフリー対策についてのお尋ねです。
天現寺橋交差点につきましては、これまでも長年にわたり、エレベーターやスロープの設置について東京都への要請を重ねるとともに、隣接する渋谷区と協議を行ってまいりました。しかしながら、現在、設置場所の確保が困難なことから、実現が難しい状況にあります。
八千代橋交差点につきましては、地元住民からの強い要請が実を結び、旧海岸通りに横断歩道が設置されましたが、札の辻側につきましては、交通管理者である警視庁から、設置が困難な状況にあると聞いております。今後も、引き続き東京都や警視庁に対し、さまざまな角度からの検討を粘り強く要請してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。