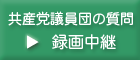2010年区議会第三回定例会
日本共産党区議団質問
日本共産党区議団の代表質問2010年9月16日
質問者 いのくま正一 議員

日本共産党区議団の一般質問
2010年9月17日
質問者 熊田ちづ子 議員

提出議案等
(略)
2010年区議会第三回定例会での質問
2010年9月16日質問者 いのくま正一 議員
1.参議院選挙の国民の審判について
2.核兵器廃絶の実現について
3.平和の灯を活かした平和行事について
4.固定資産税の引き上げについて
5.高齢者の社会的「孤立」について
6.ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン接種助成について
7.子宮頸がんワクチン接種の助成について
8.喘息患者の医療費無料化制度の改善などについて
9.障害者支援の制度改善について
10.韓国併合100年にあたり、持ち出された文化財の返還について
11.観光・文化資源を活かして街の活性化について
12.ちぃばすの利用者増の取り組みと観光発展について
13.市街地再開発事業の検証について
日本共産党港区議員団を代表して区長、教育長、議長に質問します。
最初に参議院選挙と民主党代表選挙について意見を述べます。
我党は、比例代表選挙で改選4議席から3議席に後退し、東京選挙区で議席奪還ができませんでした。
私たちは、多くの支持者や国民のみなさんの意見や思いを深く受け止め、しっかりとした総括をおこない、いっせい地方選挙、つぎの国政選挙では、必ず巻き返しをはかる決意です。
参議院選挙の結果は、消費税10%への増税を公約として打ち出し、普天間基地の沖縄県内移設を押しつけようとした民主党が大敗しました。同時に、自民党政権への復帰を求めるものではありませんでした。民主党と自民党の得票を合わせた比例選挙の得票率では、2007年参院選が68%、今回56%に12ポイントも減らしています。二大政党とも国民から支持を大きく減らしてます。
2009年の総選挙で「自公政権退場」の審判をくだしました。しかし、それに代わる新しい政治とは何かについては、探求の途上にあるのです。
「財政再建や社会保障のためには、消費税増税はやむを得ない」という大キャンペーンがマスコミを上げて行われています。民主党は、国民のきびしい審判に打撃を受けながらも、増税のための与野党協議をおこなうという姿勢です。自民党は、増税計画を独自に具体化する作業をすすめ、民主党にたいして、増税を迫っています。
国の財政危機をどうするか、いま多くの国民が不安を感じています。2010年度の国と地方での単年度財政赤字は、GDP(国内総生産)比9・4%。44・8兆円に達し、年度末の長期債務残高は862兆円、対GDP比で181%です。
財政危機をつくりだした根源は、1990年代から続けられた大型公共事業のバラマキと軍事費の膨張にあるのです。
本当の財政再建と景気回復、安心して暮らせる社会をつくるためには、人間らしい雇用のルールづくり、大企業と中小企業との公正な取引のルール確立、農林水産業の再生にむけた政策転換、社会保障の削減から本格的充実への転換などの実現こそが必要なのです。
そのために大企業の過剰な内部留保と利益を社会に還元させるとともに、国の予算を暮らし最優先にくみかえる。「ルールある経済社会」への改革によって、日本経済の危機を打開し、家計・内需主導の安定した経済成長をかちとろう、これが日本共産党が提案している「暮らし最優先の経済成長戦略」です。
歳出と歳入の改革では、無駄づかいの一掃と、特権的な不公平税制の一掃に、「聖域」をもうけずにとりくむことです。
米軍への「思いやり予算」、グアムでの米軍基地建設費負担など、世界で他に例のない費用負担もあります。それらを総点検し、大胆な軍縮のメスを入れることが重要です。
また、大企業と大金持ちへの行き過ぎた減税を「聖域」にしてはなりません。研究開発減税、外国税額控除などによって、巨大企業ほど法人税負担率が軽くなり、証券優遇税制などによって、所得1億円を超えると所得税の負担率が逆に下がるなど、特権的な大企業・大資産家優遇の不公平税制の是正を最優先でとりくむべきです。
民主党代表選の結果、菅首相が再選されました。
3カ月前に鳩山由紀夫前代表と小沢氏が「政治とカネ」問題などで辞任し、後継の菅氏も参院選できびしい審判を受けたなかでの代表選でした。
代表選では、経済や暮らしの問題でも米軍普天間基地の問題でも、国民の批判に向き合わず、政治の行き詰まりを打開する展望は示されませんでした。
菅首相は、月末にかけ臨時国会を開き、経済対策などに取り組む構えです。しかし、大企業向けの減税や普天間基地の年内「移設」に象徴されるように、財界・大企業とアメリカに忠誠を誓う路線を続けようとしています。
「異常な対米従属」「大企業・財界の横暴な支配」に縛られた政治のゆがみ=二つの異常な政治から抜け出さない限り、誰が政権の担い手になろうとも、直面している問題を解決することはできないのです。
私たちは、本当の政治改革をめざして今後とも多いに奮闘する決意です。
1、参議院選挙の国民の審判について
参議院選挙の国民の審判にもとづいて、区長に質問します。
消費税の大増税をやめるよう国に求めるべきです。
また、普天間基地の無条件撤去を国に求めるべきです。答弁を求めます。
【答弁】消費税の増税をやめるよう国に求めることについてのお尋ねです。
消費税を含む税制度の見直しについては、今後も、国の動向を注視してまいります。
次に、普天間基地の無条件撤去を国に求めることについてのお尋ねです。
普天間基地問題につきましては、国の責任で解決すべきものであり、国へ要請することは考えておりません。
議会としても同様の二つの意見書を提出すべきです。答弁を求めます。
【議長答弁】意見書の提出につきましては、各会派の皆さんと相談してまいります。
よろしくご理解いただきたいと思います。
2、核兵器廃絶の実現について
次に、核兵器廃絶の実現のため質問します。
第1に、平和市長会議の方針を区民に知らせ、協力を求めることについてです。
今年の原水爆禁止世界大会や平和記念式典は、5月にニューヨークで開かれた核不拡散条約(NPT)再検討会議の成功を受け、核廃絶の展望が具体的に見える中での開催でした。
6日の平和式典には被爆者と遺族、市民ら五万五千人が参加。潘基文(パンギムン)国連事務総長は国連のトップとして初めて参加。米国のルース駐日大使、仏と英国の臨時代理大使ら、核保有国の代表も初めて参加するなど、74カ国の政府関係者が出席しました。事務総長は、「私たちはともに、グラウンド・ゼロ(爆心地)から『クローバル・ゼロ』(大量破壊兵器のない世界)を目指す旅を続けている」と述べ、核廃絶に向けた国際的な機運を保たなければならないと呼びかけました。また、「被爆者の方々が生きている間に、その日を実現できるよう努めよう」と呼びかけました。
秋葉広島市長は、平和宣言の中で、「核兵器廃絶の緊急性は浸透し始めており、大多数の世界市民の声が国際社会を動かす最大の力」と述べ、「非核三原則の法制化と『核の傘』からの離脱」、「核兵器のない世界を一日も早く実現することこそ、人類に課せられた責務」と高らかに宣言しました。
菅首相は、式典のあいさつでは、「非核三原則の堅持を誓う」と言いながら、式典後の記者会見で、「核抑止力はわが国にとって必要」と正反対の態度を表明。非核三原則の法制化にも否定的な見解を示しました。 被爆者団体は厳しく批判。マスコミも批判的見解を示しました。
平和市長会議と広島市が主催する「2020核廃絶広島会議」が7月28日、29日に開かれました。4月に平和市長会議に加盟した港区も、担当課長が出席しました。
「広島会議」は、核兵器の全面禁止へ向けた「より強力で団結した地球的運動を」と訴える「ヒロシマアピール」を採択しました。
「アピール」は「核兵器の廃絶を目指し、市民社会や各国政府に緊急に行動」を求め、国、都市、NGO(非政府組織)、市民、国連が、核兵器の開発、実験、製造、近代化、保有、配備、使用の全面禁止の実現を提起。各国政府に核兵器禁止条約の締結交渉の即時開始、CTBT(包括的核実験禁止条約)の早期発効、核軍備近代化の停止を要求しています。「核の傘」を容認する政府へは、軍事や安全保障の方針から核兵器を排除・拒絶せよと求めています。
平和市長会が採択した「ヒロシマアピール」を区民に紹介し、その実現のための協力をお願いすること。
核兵器廃絶にむけた署名を区施設窓口に置き、区民の協力をお願いすること。 答弁を求めます。
【答弁】まず、平和市長会挙が採択した「ヒロシマアピール」についてです。
区が本年4月に加盟した平和市長会議の取組みにつきましては、広報紙や平和展等を通じ、広く区民に紹介いたしました。
平和市長会議は、本年5月の核不拡散条約再検討会議の結果を踏まえ、7月に、「2020核廃絶広島議」を開催し、核廃絶に向けた議論を行いました。この会議で採択された「ヒロシマアピール」についても、機会を捉えて紹介してまいります。
今後とも、区は、-様々な平和事業を通して、核廃絶を区民に訴えてまいります。
次に、署名用紙を区施設窓口に置くことについてのお尋ねです。
区は、平和都市宣言の理念に基づき、平和市長会議が掲げる核廃絶に向けた議定書への賛同署名を行うなど、積極的な取組みを行ってまいりました。今後とも、区として、核兵器廃絶の実現に向けた取組みを進めてまいります。
様々な団体が核廃絶を求める署名活動を行っていますが、署名用紙を区施設窓口に置くことには、慎重であるべきと考えております。
広島、長崎への原爆投下の時間にあわせ、区内のお寺などの協力を得て、梵鐘を鳴らすなど、核兵器廃絶を世論に訴える取り組みを行うこと。答弁を求めます。
【答弁】次に、核兵器廃絶を世論に訴える取組みについてのお尋ねです。
区は、毎年、原爆投下の時刻にあわせて、全区有施設で黙祷を実施し、職員や来庁者とともに、原爆死没者を追悼し世界の恒久平和を祈る取組みを行っております。また、平和の灯の破置や平和展をはじめとする様々な平和事業を通じて核兵器廃絶を区民に訴えております。
お尋ねの寺院等の梵鐘を鳴らすことにつきましては考えておりませんが、今後とも、平和事業を一層充実させるとともに、広く区民に紹介することにより、核廃絶を世論に訴えてまいります。
3、平和の灯を活かした平和行事について
次に、平和の灯を活かした平和行事について質問します。
区民の運動と党区議団の長年の提案で、区立芝公園に平和の灯(ひ){広島市の平和の灯(ともしび)、長崎市のナガサキ誓いの火、福岡県星野村(八女市)の平和の灯}が設置されました。核兵器廃絶にむけた運動の拠点にすべきです。
被爆者は高齢化しています。広島や長崎の平和式典に参加するのもままなりません。区の会議室などを利用して被爆者の追悼式を行い、平和の灯に参加者全員で献花するなど、区内被爆者のみなさんとの協議を行うべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、平和の灯を活かした平和事業についてのお尋ねです。
区は平和の灯を活用した事業として、平成19年度から、芝公園において平和コンサートを実施し、平和青年団による平和都市宣言の朗読や、広島、長崎、八女市長からのメッセージなどにより、参加した区民の皆さんの平和への思いを高めております。
また、戦没者に哀悼の意を表し、世界の恒久平和を祈る事業として、終戦記念日に、「声に出す平和への祈り」と題し、高輪区民センターにおいて朗読会を実施しております。今年度は、被爆者の方の貴重な体験談も伺いました。
今後とも、広く区民の意見を聞きながら、平和事業の充実に努めてまいります。
4、固定資産税の引き上げについて
次に、固定資産税の引き上げをやめさせるため質問します。
固定資産税をめぐっては、10数年前にも、実態とかけ離れた評価と税額が押しつけられ、区内のビルオーナーが立ち上がって、東京都に対して「高い固定資産税を引き下げよ」と不服申し立て運動が大きく取り組まれました。その結果、固定資産税の小規模非住宅用地の2割減免、小規模住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免、固定資産税の負担水準65%への軽減制度が実施されました。
ところが、ここ数年間の固定資産税がまたまた引き上がっているのです。何人ものビルオーナーの話では、昨年も今年も10%づつ税額が引き上がっています。都税事務所の話などによると、3年間、毎年10%の引き上げを行うというのです。
これでは、せっかく勝ち取ってきた、減額分が取り返されそれ以上の増税となってしまいます。
中小企業は、急激な円高によって生き残れるかどうか瀬戸際の状況です。連動してビルのテナント空きなどが広がってくれば、ビルオーナーに大打撃となり、銀行ローンをかかえている方は返済に大穴が空いてしまうのです。固定資産税の引き上げはさらに追い打ちをかけてしまうのです。
区として、東京都に対して固定資産税の引き上げをやめ、納得できる評価と税額に引き下げるよう要求するべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、固定資産税等の軽減についてのお尋ねです。
まず、固定資産税の評価と税額の引下げに関する東京都の要望についてです。
固定資産税は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、課税権者が固定資産評価額を決定し税額を算定します。評価額に対する不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対し審査の申出を行うことが可能です。
また、平成21年度から、固定資産の評価替えにより評価額が上昇した土地については、急激な税額の上昇を抑制するため、税額の上限を前年度の1.1倍とする固定資産税等の軽減措置が実施されております。
こうしたことに加え、小規模非住宅用地の税額の2割減免、商業地等の負担水準引下げなど様々な措置も講じられていることから、東京都に対し、固定資産税の評価と税額の引き下げを要望する考えはありません。
【再質問要旨】固定資産税等の軽減について
減額条例が固定資産税引き上げの原因となっている。それを正す必要があるため、働きかけをしてほしいということであり、事実認識が違っている。認識を改めて正確に答えてほしい。
【再答弁要旨】21年度の固定資産の評価替えにより、区内の地価は多くの地点で上昇している。その評価額に基づいて税額を算定すると、本来、急激に上昇することになるが、税額の上限が前年度の1.1倍に抑えられることで、軽減措置につながっていると考えている。また、小規模非住宅用地の減免等も継続するということなので、東京都に対して固定資産税の評価と税額の引き下げの要望をすることは考えていない。
議会としても同様の意見書提出を求めます。答弁を求めます。
【議長答弁】意見書の提出につきましては、各会派の皆さんと相談してまいります。
よろしくご理解いただきたいと思います。
固定資産税の小規模非住宅用地の2割減免、小規模住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免、固定資産税の負担水準65%への軽減制度を来年度以降も継続するよう東京都へ要望するべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、固定資産税等の軽減措置の継続に向けた東京都への要望についてのお尋ねです。
23区内の土地の固定資産税等の軽減措置につきましては、平成14年度から小規模非住宅用地の税額の2割減免、平成17年度から商業地等の負担水準引下げが継続されております。
固定資産税等の軽減措置の継続に向けた要望につきましては、東京都の動向を踏まえ、適切に対応してまいります。
議会としても同様の意見書提出を求めます。答弁を求めます。
【議長答弁】意見書の提出につきましては、各会派の皆さんと相談してまいります。
よろしくご理解いただきたいと思います。
5、高齢者の社会的「孤立」について
次に、高齢者の社会的「孤立」をなくすために質問します。
全国各地で高齢者の所在不明が問題になっています。貧困と格差の広がりの中で、家族を含め社会から断ち切られた高齢者の「孤立」という深刻な社会状況が背景にあります。9月5日放送のNHKスペシャルでは、所在不明者の多くが地縁や血縁など社会とのつながりを失ったまま「無縁化」していること。どこでも起こりうる状況にあり、病気や失業による貧困が家族を崩壊させ、高齢者に限らず所在不明者を生み出していると報道しました。
法律では自治体に高齢者の実態把握の責務を明記しています。
住民基本台帳法では「市町村長は、定期に、第7条(住民票の記載事項)に規定する事項について調査をするものとする」。老人福祉法では、市町村長は「老人の福祉に関し、必要な情報の把握に努める」と定めています。
自治体による高齢者の安否確認や見守りなどの支援体制が問われてれているのです。
新宿区では今年度から地域包括支援センターを高齢者総合相談センターと名称も変えて地域の高齢者を総合的に見守れるよう、予算を前年度の4倍、人員も2倍に増やしています。
千代田区では、90歳以上の在宅高齢者を対象に、来年度から年2回の「(仮称)長寿高齢者御用聞き・見守り訪問」を行うと発表しています。
区として高齢者を直接面接して安否確認を行う見守り支援体制をつくること。
ごみの戸別訪問収集事業など見守りを伴う事業の拡大を図ること。
答弁を求めます
【答弁】次に、高齢者の社会的「孤立」をなくすことについてのお尋ねです。
まず、高齢者の面接による安否確認を行う見守り支援体制をつくることについてです。
高齢者の生活の安心確保には、民生委員や町会・自治会を始めとする高齢者に身近な地域コミュニティの力が大切と考えております。
このため、港区高齢者地域支援連絡協議会や各地区に高齢者支援連絡会を設置し、地域の活動主体と区との連携や情報の共有化を図ってまいりました。
また、地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として、地域の高齢者を訪問し、様々な相談等を通じ必要なサービスにつなげております。
今後、区は、保健福祉基礎調査の結果を踏まえ、地域包括支援センターの充実も含め、地域コミュニティの力を活用した支援体制を検討してまいります。
次に、ごみの戸別訪問収集事業など見守りを伴う事業の拡大についてのお尋ねです。
現在、区は、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に対して、見守りができるごみの戸別訪問収集や配食サービス、家事援助サービス、緊急通報システム、訪問電話などの事業を実施しております。
今後、保健福祉基礎調査結果を踏まえ、見守りを伴う事業の充実に努めてまいります。
高齢化がすすむ新宿区の戸山団地で孤独死を無くすため、地元のNPO法人「人と人をつなぐ会」が携帯電話による見守りサービスを始めました。ワンタッチボタンの付いた携帯電話とコールセンター会社「愛ことば」のサービスを利用して24時間受け付けます。ボタンを押すと、センターの係が「体調が悪い」「困り事ができた」などの事情を聞き、適切な相談場所に転送します。事前登録したかかりつけ医や知人にもつながります。朝一番に電話を開いた時、親戚や知人に、自動的にメールで「健在」を知らせる仕組みもあります。
緊急通報システムは、現在839世帯に設置され出動回数382件で37名が救助されるという大切なシステムですが、誤作動・誤報が345件もあります。人とつながらないシステムの結果です。
一方、携帯電話による見守りサービスは、人とのつながりを感じられます。緊急通報システムにかわるシステムとして注目すべきものです。早急に導入を検討すべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、携帯電話による見守りサービスについてのお尋ねです。
区は、高齢者の見守り事業として、定期的に電話をし、相談と安否確認を行う訪問電話事業や緊急時に警備員が直接駆けつける緊急通報システム事業を実施しております。
また、地域包括支援センターでは、365日、24時間電話での相談を受けております。
今後も、区は、人と人との繋がりを大切にし、地域コミュニテイの力を活用し、見守り事業を充実してまいります。
携帯電話による見守りサービスについては、今後、検討してまいります。
6、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン接種助成について
次に、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン接種助成について質問します。
細菌性髄膜炎は、乳幼児に重い後遺症を引き起こしたり、死亡する恐れが高い感染症で、その原因の75%がヒブと肺炎球菌によるものです。細菌性髄膜炎は、早期診断が困難で発症後の治療にも限界があり予防が重要です。
ヒブや肺炎球菌による細菌性髄膜炎については、乳幼児期のワクチン接種で予防が可能です。
世界保健機構(WHO)もワクチンの定期接種を推奨し、すでに欧米、アジア、アフリカなど110カ国以上で導入。90カ国以上で定期予防接種がおこなわれ、発症率が大幅に減少しています。
日本では、世界から20年遅れで、2008年12月からヒブワクチンが販売開始となり、小児用肺炎球菌ワクチンも、昨年10月に国内承認され、今年2月から任意接種が始まりました。
費用負担が大きいため、多くの自治体で助成が始まり23区ではすでに18区が助成しています。
1.国に対し、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの定期接種を実施するよう求めること。
2.それまでの間、港区として接種費用を無料にすること。答弁を求めます。
【答弁】次に、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン接種費用の助成についてのお尋ねです。
まず、国に両ワクチンの定期接種実施を求めることについてです。
ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、現在、国の予防接種部会において、定期接種化した場合の効果について検討中です。
区としても、全国保健所長会を通じて、公衆衛生上必要となるワクチンについては、科学的根拠に基づいて定期接種化を実施するよう、国に意見書を提出しております。
次に、区として接種費用の無料化を実施することについてです。
ヒブワクチンにつきましては、今年4月から、国の予防接種部会において、既に助成を実施している自治体でのワクチンの効果や安全性を踏まえて、定期接種化への検討を進めているところです。
現在、他の自治体が実施している中で、特に重大な副反応は認められておらず、区としましても、国の動向を見ながら、接種費用助成を実施する方向で検討してまいります。
小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、接種が開始されて日が浅く、安全性の確認が十分とはいえない状況です。
区民が安心して接麺を受けられることが最重要と考えますので、国の予防接種部会の動向を見守りたいと考えております。
7、子宮頸がんワクチン接種の助成について
次に、子宮頸がんワクチン接種の助成について質問します。
子宮頸がんはワクチン接種で予防できるただ一つの癌です。多くの自治体で助成がはじまり、23区では5区で実施しています。国も接種費用の助成(実施自治体へ3分の1補助)を概算要求に盛り込んだとの報道もあります。
子宮頸がんは20代から30代の女性に多く発症し、乳がんについで多く、日本では30代をピークに年間1万5千人が罹患し、3500人が死亡しています。
日本産婦人科学会、日本小児科学会、日本婦人科腫瘍学会が合同で、ワクチン接種の必要性、公費負担の必要性を訴えています。
2006年に米国で承認後、現在100カ国以上で接種されています。日本でも接種が可能となりましたが、任意接種のため費用が3万円から5万円と高額です。
子宮頸がんワクチン接種の公費負担については、自治体による格差、貧富の差による医療差別が生じないよう全額国で実施するよう求めるべきです。
港区議会では、第2回定例区議会で請願が採択されています。区として全額助成を決断すべきです。
それぞれ答弁を求めます。
【答弁】次に、子宮頸がんワクチン接種費用の助成についてのお尋ねです。
まず、全額公費負担を国に求めることについてです。
子宮頸がんワクチンは、現在、国の予防接種部会において、定期接種化した場合の効果について検討中です。
区としましても、全国保健所長会を通じて、科学的根拠に基づいて、定期接種化を検討すること、また、接種費用の負担については、地域格差等が生じないよう、国に意見書を提出しております。
したがいまして、現時点では、国の動向を見守ってまいります。
次に、区で全額助成することについてのお尋ねです。
子宮頸がんワクチンは、すべてのヒトパピローマウイルの感染を防げるものではないなど、検討を要する点もあります。
しかし、がんを予防できる可能性のある唯一のワクチンであり、学校教育との充分な連携による啓発、及び、がん検診を組み合わせることにより予防効果が認められること、また、接種費用が高額であり負担が大きく、国も一定の効果を認め、来年度から一部助成の開始の検討を始めており、接種費用助成を実施する方向で検討してまいります。
8、喘息患者の医療費無料化制度の改善などについて
次に、喘息患者の医療費無料化制度の改善などについて質問します。
「東京に青空ときれいな空気をとり戻す」ことを目的に結成された東京青空連絡会は、長期にわたる裁判闘争や住民運動を行ってきました。その運動が実り、東京都の制度として喘息患者の医療費無料化が実現しました。喘息患者の治療と生活にどのような役割を果たしたかを、4人の研究グループが調査した結果、「無料制度は本当にありがたい。お金を心配せずに医者にかかれるので、気も楽だし体も良くなったような気がする」との回答が72%にもおよび、「自分の病気が公害によるものだと認められて良かった」など精神的な負荷が軽減されたとの回答も目立っています。
しかし、改善すべき点もあります。一つは、医療費無料の制度が周知徹底されていないことです。認定数を見ると、23区全体で32、239件人口比率では0.004%です。港区では認定数が450件、人口比で0.0025%と平均よりも極端に低くなっています。
区内にも喘息で苦しんでいる方が数多くいます。この方々に医療費無料制度を周知徹底すべきです。くりかえし広報みなとで周知するとともに、ホームページや支所や区施設に掲示したり、また区内の医療機関にもポスターやビラの宣伝をお願いするなど、確実に制度周知を徹底してもらいたい。答弁を求めます。
【答弁】次に、喘息患者の医療費無料化制度の改善についてのお尋ねです。
まず、確実な制度の庵知徹底についてです。 東京都大気汚染医療費助成制度については、東京都が医師会、薬剤師会へパンフレット、ポスター配布を依頼し、東京都広報に掲載するなど周知を行っております。
また、区におきましても、パンフレットを各地区総合支所の窓口に配置するとともに、広報みなとや区ホームページに掲載して周知しております。
今後も、新たに、区掲示板にポスターを掲出するなど、制度の周知について、さらに努めてまいります。
二つ目は、現在の東京都の医療費無料制度を国として実施すべきということです。喘息患者は東京都だけではありません。自動車交通量の増加による大気汚染は首都圏全体に広がっているのです。
区として、国に医療費無料制度を実施するよう要求するべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、国に医療費無料化を求めることについてのお尋ねです。
現在、東京都では大気汚染医療費助成制度により、喘息患者について医療費無料化を実施しております。
喘息の発生メカニズムには、大気汚染以外にも多くの要因が絡んでおり、また、それぞれの地域による環境も異なることから、全国一律の対応は難しいと思われるため、国に医療費無料化を求めることは考えておりません。
三つ目は、大気汚染の大きな原因の一つである、自動車製造責任を問う事です。トヨタ自動車など大手自動車産業に対して、排ガス公害の責任を認め救済制度の財源を負担せよの世論を広げていくことが重要です。区として、大手自動車産業に要求するべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、大手自動車産業に財源の負担を求めることについてのお尋ねです。
東京都大気汚染医療費助成制度では、すでに自動車メーカーが財源の一部を拠出していると承知しております。
9、障害者支援の制度改善について
次に、障害者支援の制度改善について質問します。
喘息患者の医療費無料制度について区民から相談を受けました。その時、関連して区の障害者支援の制度が適用にならないか、調べてみました。この相談者は「呼吸器障害3級」でした。区の制度では、障害者福祉手当月額7750円の支給対象になります。その他の制度は適用になりませんでした。矛盾を感じたのは、タクシー利用券の支給対象にもならない点です。区の対象条件は、「身体障害者手帳の交付を受けた、下肢、体幹、視覚1~3級。内部障害1級の人」と規定しています。呼吸器障害3級のこの方は、外出時も含め酸素ボンベを常時つけています。病院に行くにもタクシーを使って移動しているのです。実態と制度が矛盾しているのです。
自動車燃料費助成制度も同様の対象条件です。この場合も、障害をもつことによって、自動車なら移動できるという理由から、燃料代を支給しているのだと思います。
現実と制度が矛盾しないように、実態に合わせて制度改善するべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、障害者支援の制度改善についてのお尋ねです。
まず、タクシー利用券と自動車燃料費助成の支給対象についてです。
内部障害の呼吸器機能障害につきましては、支給対象となっている1級の方と比較し、3級の方は家庭内での日常活動が著しく制限されるものの、区としては酸素ボンベを携行していれば移動が可能と判断し、3級は支給対象としておりません。
今後、呼吸器機能障害者の実態把握に努めてまいります。
【再質問】障害者支援の制度改善について
タクシー利用券について、しっかりとニーズを聞いて実現させてほしい。
【再答弁要旨】呼吸器機能障害者の実態把握に努める。
障害者支援の他の制度についても、この際矛盾がないかどうか、改善への総点検を行うべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、障害者支援制度の総点検についてのお尋ねです。
これまでも、障害ケースワーカーによる訪問や総合支所での相談、障害者と区長との懇談会での障害者団体などからの要望等から、生活状況や障害者ニーズの把握に努め、制度の充実を図ってまいりました。
今後も、障害者支援制度について、障害者の方の生活状況やニーズを的確に把握し、総合的な障害者施策の充実に努めてまいります。
関連して、精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給するため質問します。
区は、精神障害者から手当の支給に関した要望が出ていないことを実施しない理由にしてきました。今年6月に区民から区に対して要望が出されました。
姉が精神障害者福祉手帳2級をもっている、妹さんからの要望です。目に見えない、記憶障害、思った言葉が出ない、意味がわからない、などの特殊性があり通院しているが、自立した日常生活を豊かにするためにも、外に出て社会とのつながりが大事なことと思っている。そのためにも精神障害者に手当の支給を強く要望しています。
これに対して、区は、「手当の要望があることは承知しておりますが・・・障害者グループホームの設置および整備支援、日中活動の場の確保、社会参加の拡大や就労支援の強化など、経済的支援をより優先して施策の充実にとりくんでいます」などと答えているのです。「手当の要望があることを承知している」のであれば、正面から受け止めて、早急に精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給すべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、精神障害者への心身障害者福祉手当の支給についてのお尋ねです。
区は、住み慣れた地域で、安心して暮らせる社会を実現するための障害者グループホームの設置の取り組みや、社会参加の拡大や就労支援を強化するための、福祉売店「ろぜはーと」を本年6月に開設するなど、精神障害者から要望の強い施策の充実を優先し、推進しております。
精神障害者を心身障害者福祉手当支給対象とすることにつきましては、検討課題と考えております。
10、韓国併合100年にあたり、持ち出された文化財の返還について
次に、韓国併合100年にあたり、持ち出された文化財の返還について質問します。
日本が朝鮮半島を植民地化した「韓国併合」から8月22日で100年になりました。
「韓国併合条約」は、日本が韓国に対して、軍事的強圧によって一方的に押しつけた不当・不法な条約であり、植民地支配によって国を奪い、文化を奪い、言語を奪い、創氏改名により名前すら奪ったことを、日本国民は忘れてはなりません。それを両国の共通の歴史認識とすることが、未来にとって重要です。過去の誤りを真摯に認めてこそ日本は未来に向かってアジア諸国民との本当の友情を得ることがきると確信します。
政府は「韓国併合」100年に当たっての首相談話で「痛切な反省とおわび」を表明し「これからの100年を見据え、未来志向の日韓関係を構築」していくと強調しました。また、朝鮮王朝の主要行事を絵や文書で記録した古文書の「朝鮮儀軌(ぎき)」を「返還」でなく「引き渡す」と述べました。「文化財は原産国に戻す」というのは、ユネスコの条約でも原則とされていることであり、「儀軌」を出発点として文化財が返還されることを願うものです。
7月に、虎ノ門の私立美術館「大倉集古館」にある五重石塔の返還を求め韓国・利川(イチョン)市から、市民の半分に当たる10万人の署名を持って代表団が来日し「石塔は千年にわたって利川の地にあったもので、市民にとって精神的な支柱をなしてきた。ぜひ元の場所に返してほしい」と訴えました。五重石塔は現在、日本の重要美術品に指定されており、国外に持ち出す場合は政府の許可が必要となります。
港区には韓国大使館があります。外国人登録者のうち韓国および朝鮮の方が2位を占めており、友好を積極的にすすめるべきです。
①区は五重石塔の返還ができるよう関係者に要請すること。
②政府に文化財の国外持ち出しを許可するよう要請すべきです。
答弁を求めます
【教育長答弁】最初に大倉集古館の五重石塔についてのお尋ねです。
まず、関係者への要請についてです。
国が所有する文化財の引渡しについては、現在、政府が検討を進めており、その動向を見守ってまいります。
なお、大倉集古館所蔵の文化財につきましては、故大倉喜八郎氏個人が、正式な手続きを経て輸入されたものと伺っておりますので、関係者への要請を行うことは考えておりません。
次に、文化財の国外持ち出しの許可を要請することについてのお尋ねです。
文化財保護法第44条に定められた輸出の禁止の規定により、国指定文化財の輸出は禁止されておりますが、条件が整えば文化庁長官の許可を得て持ち出しは可能となります。
文化財の国外持ち出レは、所有者と博物館等利用者の合意によって許可申請を行うものですので、区が、国に要請することは考えておりません。
11、観光・文化資源を活かして街の活性化について
次に、観光・文化資源を活かして街の活性化をはかるため質問します。
本年第1回定例会で私ども提案した、来年のNHKの大河ドラマ「江 ~姫たちの戦国~」を区の観光と商店街発展に活かす問題です。
お江は、織田信長の妹・お市の方の三女で、徳川二代将軍・秀忠の正室、三代将軍・家光の生母です。増上寺に埋葬されています。
現在、増上寺の将軍墓にある秀忠の石塔は、お江の旧墓塔です。秀忠の木造宝塔が戦災で焼失したため、お江の宝塔が使われています。
大河ドラマ化が決まった直後、滋賀県、福井県、三重県が早々と観光や地域の活性化にむけ動きだしたことはすでに紹介してきたとおりです。
その後も各県は、活動を具体化し、お江関連の観光ツアーコースを考案し、すでに実施されています。例年の観光客の1.5倍ほど人気が出ているそうです。また、イメージキャラクターを考えるなど活発化しています。
港区でも教育委員会、港区、観光協会、区商連、増上寺と具体的な協議を行い、大きな成果が得られるよう進めるべきです。現在までの協議状況と今後の取り組みについて説明を求めます。
【答弁】大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」を活用した観光振興の協議状況等についてのお尋ねです。
区は、本年6月、大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」を活用した観光振興を図るため、教育委員会、港区観光協会、港区商店街連合会、増上寺を委員とする「お江記念事業検討委員会」を設置いたしました。
検討委員会では、本年11月に開催する「ものづくり・商業観光フェア」で実施するまち歩きイベントの際に増上寺の徳川将軍家霊廟を特別に公開するなど、相互に連携、協力して効果的に事業を実施することを確認いたしました。
また、港区観光協会では、歴史観光シンボルとして、イメージキャラクター「お江姫」を作成し、関連事業やオリジナル商品作りに活用することとしております。
今後も継続して検討委員会を開催し、関係機関相互の連携を深め、事業の計画や効果的な実施に向けて協議を進めてまいります。
お江は、亡くなった後、我善坊(麻布台1丁目)で火葬され、増上寺に埋葬されました。徳川将軍家の中で火葬は最初で最後です。火葬から増上寺までの行列の様子も予算委員会で紹介したとおり、「その香煙は1キロ以上にわたってたなびいた」という壮大なものでした。
寛永五年に三回忌の法事を勤めたのが教善寺などと資料があります。教善寺は、現在、六本木5丁目にあります。お江の火葬や行列の様子が記されている文献などもあるかも知れません。情報提供をお願いし、資料収集するべきです。他にも港区とお江のゆかりについて、郷土資料館を中心に資料を収集するべきです。その資料を広く宣伝周知するとともに、産業振興課と連携を強め、文化の継承と区の活性化にも生かしていくべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、お江関係資料の収集・活用と新郷土資料館についてのお尋ねです。
まず、お江関係資料の収集と活用についてです。
港郷土資料館では、徳川将軍家・増上寺関係資料を、所蔵資料の中核をなす柱の一つと位置付け、資料の収集を進めております。お江関係資料につきましても、その一環として注視しているところです。
お江は逝去後、我善坊谷周辺で茶毘にふされましたが、その後、茶毘所の跡地には教善寺、深広寺、光専寺が移され、今に続いております。いずれの寺院も、お江が生きた江戸時代前期の港区を知る上で重要です。
教育委員会では、これら寺院ならびに関係機関の協力を得て、お江関係資料・情報の収集を進めてまいります。
なお、資料・情報につきましては、関係機関と連携しながら、公開・活用に努めてまいります。
関連し、長年棚上げ状態となっている、郷土資料館の建設について早急に建設地を検討・確定すること。答弁を求めます。
【答弁】最後に、新郷土資料館の建設地についてのお尋ねです。
新郷土資料館建設地につきましては、多くの来館者を迎えることができ、歴史や文化を通して港区をよく知っていただくための活動を行うのに適した場所である必要があります。交通の利便性に富み、多くの文化財に囲まれた文化の香り高い環境であること、何よりも気軽に来館できることが、最適な立地条件といえます。
こうした条件を備えた適地を、なかなか見出せずにいるのが現状ですが、新郷土資料館建設地の早期確定にむけ、今後とも区長部局と連携を図りながら努力してまいります。
12、ちぃばすの利用者増の取り組みと観光発展について
動次に、ちぃばすの利用者増の取り組みと観光発展について質問します。
ちぃばすの新5路線がスタートして半年が経過しました。利用実績は、5ルート全体で4月の119,501人から7月は180,248人へと1.5倍に向上しています。運行開始から区民などに周知され「100円で病院や支所買い物にも行ける。とても便利」の声が寄せられています。さらに利用者を拡大して安定運行の努力が必要です。
そのためにも、また、区の観光と商店街活性化のためにも、次の提案を早期に実施するよう求めます。
先の質問にも関連しますが、港区には歴史的文化財や観光名所が随所にあります。私どもが以前提案し作成されてきた「港区観光マップ」がありますが、ちぃばすを利用して区内の文化や観光巡りができる、「ちぃばす観光マップ」を作成し利用促進をはかるべきです。一日乗車券も活用して「ちぃばす スタンプラリー」なども企画できればより良い取り組みになると思います。
これらを早期に検討具体化すべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、ちぃばすの利用者拡大への取組みと観光振興についてのお尋ねです。
まず、「ちぃばす観光マップ」と「ちぃばすスタンプラリー」による利用促進についてです。
区では、今年度から発行を開始した観光情報誌「ハレノヒ」の中で、ちぃばすによる観光案内のコラムを設け、テーマに沿った観光スポットや隠れた観光資源などを継続的に紹介し、好評をいただいております。
また、今後は、バス停付近における散策マップの設置も予定しています。
ご指摘の「ちぃばす観光マップ」や「ちぃばすスタンプラリー」等のイベント企画につきましては、他のバス事業者等の企画も参考にしながら、調査・研究してまいります。
【再質問要旨】「ちぃばす観光マップ」と「ちぃばすスタンプラリー」による利用促進について
調査・研究ということではなく、実施する方向で検討するなど態度を明確にしてほしい。
【再答弁要旨】都バスでは、一部の路線で人気アニメの劇場公開や人気キヤラクターの宣伝に併せたスタンプラリーが実施されている。このような事例を参考にしながら、調査・研究をしていく。
ちぃばすのバス停の追加や終点で降ろされる問題等々、議会各会派から「改善要望」を提出しました。すぐ実現できる中身もあるはずです。要望に対する検討状況はどうなっているか。答弁を求めます。
【答弁】次に、ちぃばすの改善要望に対する検討状況についてのお尋ねです。
ちぃばすの新規5路線の実証運行を本年3月に開始してから、利用者から多くのご意見や要望をいただいております。また、7月には区議会の各会派から改善要望をいただきました。
終点で一旦降車することへの改善要望につきましては、麻布ルート、高輪ルートにおいて、終点を越えて乗り越しができるよう6月下旬から改善を図りました。
バス停留所の追加につきましては、交通管理者、道路管理者、沿道の方々との調整を進めており、バス停留所の名称変更等その他の課題とあわせて、今後、港区地域公共交通会議に諮り、順次取り組んでまいります。
>
13、市街地再開発事業の検証について
最後に、市街地再開発事業の検証について質問します。
今年、4月15日の都市計画審議会で、学識経験者委員から、「この間区内で行われてきた再開発について、どういう問題がおこっているか、検証委員会をつくって検証するべき」という提案がありました。街づくり支援部長は、「何ができるか、検討させて頂きたい」と検討を約束しました。
常識的に見て、この答弁の方向は、「まともな検証がされるのだろう」と誰もが思うはずです。ところが、私どもが前定例会で、再開発の検証を質問したところ、副区長は、再開発事業は、災害に強い街づくりのため、地域に貢献する道路、緑地などの公共・公益施設の整備や住宅の確保など、高い公共性を備えたまちづくりの手法で、区は、事業内容などを適切に評価した上で、再開発事業を支援している」などと、再開発事業の有効性と今後も推進する姿勢を示した上で、「評価検証する仕組みについて検討を深めていく。検証すべき事項、調査内容についても、その中で検討していく」と答えています。
簡潔に言えば、再開発は公共性が高い事業。だから区が支援している。再開発は必要。その立場で検証する。というものです。
これでは、本当の検証はできません。私たちはくり返し指摘し質問してきたように、再開発事業によって、多くの区民が転出したことや、環境破壊、大規模地震時には安全でないこと、地域コミュニティーが破壊されているのです。再開発事業自体に多くの区民は、疑問・反対の声を上げているのです。
再開発の検証にあたっては、「再開発は必要」という規定概念を取り払い、住民・地権者の動態や環境への影響、災害時の安全、コミュニティー等々を正確に検証すること。また、区民が再開発事業をどう考えているかも調査すべきです。明確に答弁を求めます。
【答弁】次に、市街地再開発事業についてのお尋ねです。
まず、市街地再開発事業の検証についてです。
市街地再開発事業は、良好な都市環境の創造や、災害に強い街づくりのため、公共・公益施設の整備や住宅の確保、さらには商業や、業務、文化などの各機能が調和した、将来にわたり安全・安心なまちを実現する、都市計画法や都市再開発法に基づく法定事業です。
この事業は、地区内の様々な地権者の方々が主体となって市街地再開発組合を設立し、計画段階から組合設立、権利変換、管理運営まで係わることのできる共同事業でもあり、地域の方々自らが取り組む、高い公共性を備えた、まちづくりの効果的な手法の一つと考えております。
これまでも区は、都市機能の更新状況や事業効果、都市計画の目標の実現状況等を確認し、まちづくりの成果をその後に実施される事業への指導の中で生かしてまいりました。
市街地再開発事業の検証につきましては、全国的に見ても公開されている事例が少なく、また、私有財産を扱う事業ということから情報収集も難しい点がありますが、今後も、評価検証する仕組みや内容について検討を深めてまいります。
【再質問要旨】市街地再開発事業の検証について
検証にあたり、具体的に人口動態やコミュニテイ、環境の問題などを総合的に、規定概念なしに検証することが大事。
検証をいつ行うつもりなのか。
【再答弁要旨】現在、それぞれの再開発事業の進捗が適切であったかどうか、また、地区内の人口動態の調査等を実施している。
今のところ、基礎的な情報の収集に努めている段階だが、今後も評価・検証する仕組みや内容について検討を深めていく。
区は、森ビルや三井不動産など大企業が進める再開発事業に、過去27年間238億円の補助金を出し、今後は、9年間で280億円もの税金を投入する計画です。規模とスピードを大幅に引き上げています。
圧倒的な区民の声は、「何故森ビルなどに補助金を出すのか。やめるべきだ」と声を上げています。森ビルなどへの再開発補助金はキッパリと中止するべきです。答弁を求めます。
以上で質問を終わります。答弁によっては再質問いたします。
【答弁】最後に、市街地再開発事業の補助金についてのお尋ねです。
区は、高い公共性を備えた市街地再開発事業を支援するために、事業規模や権利者数の大小を問わず、事業内容などを適切に評価した上で、都市再開発法や港区市街地再開発事業等補助金交付要綱に基づいて、事業を支援しております。
今後も、権利者の方々の合意形成に基づき、共同してまちづくりを進めていく、市街地再開発組合等に対しての補助金は必要と考えております。
以 上
2010年区議会第三回定例会での質問
2010年9月17日質問者 熊田ちづ子 議員
1.保育園の待機児問題の早期解消について
2.後期高齢者医療制度について
3.介護保険制度について
4.総合的な熱中症対策について
5.白金6丁目の建築問題について
日本共産党港区議団の一員として区長に質問します。
1、保育園の待機児問題の早期解消について 最初に、保育園の待機児問題の早期解消についての質問です。
厳しい社会状況下で、働く女性も増え、保育園問題は深刻です。待機児童数は、8月1日現在、旧基準で920人、と依然として多く、来年4月まではもっと増えることになります(4月当初の待機児912人)
区はこれまで我が党の質問に対し、認可保育園3園の整備、改築による定員拡大、5カ所目の暫定保育所の整備により、大幅な待機児童の解消につながると答弁しています。しかし、入所相談や、保育園の見学者は多く、入所希望者が増え続けています。
公立保育園の建設抜きには解決できません。早急に公立保育園の建設を行うべきです。答弁を求めます。
【答弁】保育園の待機児童問題の早期解決についてのお尋ねです。
まず、早急な公立保育園の建設についてです。
区は、平成16年度以降現在までの間、待機児童解消に向け、緊急暫定保育施設の設置により約600名、認証保育所の誘致により約520名の定員拡大を図ってまいりました。
しかしながら、社会経済状況の変化や人口増加による子育て世帯の増加により、8月1日現在、待機児童数は、前年同月に比べ67名減少したものの218名と依然として解消には至っておりません。
現在、旧神明運動広場、港南四丁目、田町駅東口北地区に認可保育園3園の建設整備と5園の改築、認証保育所2ケ所の誘致により、合計約700名の定員拡大を図る計画です。
今後とも、待機児童解消を目指し、区立認可保育園のみならず緊急暫定保育施設の継続や増設の検討、認証保育所の更なる誘致など、多様な手法により定員拡大を図ってまいります。
暫定保育室は、5カ所目が開設し、定員も605人にまで増え、待機児解消に大きな役割を担っています。しかし、あくまでも期限付きの暫定施設なため、途中での退園など、利用者への負担や不安は大きいです。東麻布保育室は、保護者から暫定期間の延長を求める陳情や請願が出されています。地元の学校跡地検討会からも残してほしいとの要望が出されています。
区はこれまで「待機児の状況を見て検討する」と答弁していますが、待機児は増え続けており、廃止できる状況ではありません。
①東麻布保育室を継続すべきです。また、高輪保育園の仮園舎についても継続使用すべきです。
②暫定保育室の建設は、計画から半年ぐらいで建設できます。来年4月からの待機児をなくすために国公有地を活用し、早急に建設すべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、東麻布保育室の継続についてのお尋ねです。
東麻布保育室は、旧飯倉小学校の校舎を利用した緊急暫定保育施設として、平成19年10月から平成24年3月までの期間を限定して開設いたしました。
区は、これまで区立保育園の改築、緊急暫定保育施設の増設や認証保育所の誘致などにより定員拡大を図ってまいりましたが、依然として待機児童解消には至っておりません。
待機児童解消に向け、改めて緊急暫定保育施設の継続や増設、認証保育所の更なる誘致など保育施設の今後のあり方について幅広い検討が必要と考えております。東麻布保育室につきましては、こうした状況を勘案し、継続の方向で検討してまいります。
次に、(仮設)高輪保育園の継続使用についてのお尋ねです。
現在、高輪保育園を含め、認可保育園5園の改築による定員拡大を図っております。
高輪保育園は、東京都の土地を活用し、仮設を設置しているものです。
仮設の継続使用には、課題もあり慎重な検討が必要ですが、仮施設の取り扱いや借用期間の延長などを検討しております。
今後も、引き続き継続使用の方策を検討し、待機児童の解消に努めてまいります。
次に、国公有地を活用した緊急暫定保育施設の増設についてのお尋ねです。
区はこれまでも待機児童解消に向け、認可保育園3園の建設整備や5園の改築による定員拡大に取り組んでおります。また、民間の土地取得や都有地の活用により、緊急暫定保育施設の整備や認証保育所の誘致を進めてまいりました。
現在も、緊急暫定保育施設等に適した国公有地を調査しておりますが、現段階では適当な用地がありません。
今後とも、待機児童の地域の状況等を分析し、国公有地等の活用について検討してまいります。
これまで区は、待機児解消の一つとして、定員の弾力化を行ってきました。
導入からすでに7年(H16年)、現在は弾力化で保育園を利用している方は139人にまで増えています。公立保育園2園分に当たります。芝保育園は定数164人で職員数は26名です。港南保育園は定数は146名ですが弾力化をあわせると161名で職員数は24名です。同程度の子どもの数がいながら職員は2名少なく、園児にとっても職員にとっても、大きな負担になっています。
定員の弾力化はやめ、きちんと定数化し、必要な職員を配置すべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、定員の弾力化についてのお尋ねです。
保育園定員の弾力化は、児童福祉施設の国基準に基づく必要な水準を確保しながら、受け入れ体制のとれる保育園において定員を超えて保育の実施を行い、待機児童解消を図ることを目的として、公立保育園11園、私立保育園4園にて実施しております。
今後とも、保護者の方が安心して働き、子育てができるサービス水準を維持しながら、待機児童の解消に努めてまいります。
渋谷区が所得400万円以下の世帯の保育料を無料にし、1千万円以下の世帯の保育料を所得に応じて減額しました。
私たちは第2子以降の保育料無料化と合わせ、港区でも実施するよう求めてきました。
区は、「待機児童の解消になっていないから保育料の減額や無料化は考えていない」との答弁ですが、待機児を放置しているのは区の責任です。経済的支援をやらない口実にするのは、本末転倒です。
子育て世代の多くは長引く不況の下で、経済的に厳しい状況におかれています。子育て世代の負担軽減のために、渋谷区などの先進区を参考に保育料の軽減を図るべきです。
①認可・認証保育園、認可外保育園の保育料を所得400万円以下の世帯については無料にすること。所得1千万円以下の世帯の保育料を段階的に減額すべきです。
②第2子以降の保育料を無料にすべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、世帯の収入に応じた保育料の軽減についてのお尋ねです。
社会経済状況の変化や人口増加による子育て世帯の増加により、現在のところ、待機児童の解消には至っておらず、引き続き定員の拡大が重要課題と考えております。
こうしたことから、認可保育園及び認証保育所の保育料の減額及び無料化は、現在のところ考えておりません。
次に、第2子以降の保育料の無料化についてのお尋ねです。
認可保育園での保育料は、第2子以降の方には所得に応じた減額を行っており、さらなる保育料減額は現在のところ考えておりません。
2、後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度について質問します。
75歳という年齢で差別する、後期高齢者医療制度の廃止を求める声は、大きく広がっています。今年度の保険料は均等割(37,800円)が据え置かれたものの所得割が引き上げられ39%の人が値上げされました。
2010年8月20日、高齢者医療制度改革会議が決定した、「新制度」の中間のまとめでは、高齢者を差別して負担増と医療抑制を強いる後期高齢者医療制度の根幹を残すものとなっています。批判の強かった、サラリーマンとして働く高齢者やサラリーマンの家族に扶養されている高齢者は組合健保や協会健保等の被用者保険に入るものの、それ以外の約8割の高齢者は国保に加入、現役世代と別勘定とする内容です。
別勘定の年齢を現在の75歳以上とするか、65歳以上とするか、国保の運営主体を広域化するかは今後の検討課題としています。
国民の大きな批判になっている年齢での差別と負担増を、より拡大することになり、総選挙での公約違反は明らかです。
安心して必要な医療が受けられるようにするために、後期高齢者医療制度は、廃止するよう 国に求めるべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、後期高齢者医療制度についてのお尋ねです。
まず、後期高齢者医療制度の廃止を国に求めることについてです。
国は、「高齢者医療制度改革会議」のもと、今年8月に、後期高齢者医療制度廃止後の新たな高齢者医療制度についての「中間とりまとめ」を示しました。
これに対し、特別区長会は、真に抜本的な改革案を取りまとめ、国民や地方自治体の合意を得て検討を進めるよう緊急の申し入れを行ったところです。
こうしたことから、国に制度の廃止を求めることは考えておりません。今後も、国の動向を注意深く見守り、適切に対応してまいります。
当面の課題として2年後には、もう一度保険料改定が行われます。これを受けて広域連合協議会は、6月7日に国に対し、要望を出していますが、まともな回答はないとのことです。港区としても、「これ以上の負担増はしない、負担軽減を図る」との立場にたち、国と東京都に負担を求めるべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、国と東京都に負担を求めることについてのお尋ねです。
本年8月の特別区長会の緊急申し入れの中で、今後増加し続ける高齢者の医療費について、国が責任を持って対応する姿を示すよう、求めております。
区といたしましても、2年後の保険料改定を含め、今後とも、被保険者の負担増を最大限軽減するよう、国や東京都に対して、特別区長会などを通じて要望してまいります。
東京都広域連合の2009年度の滞納者は39,460人。滞納率は3.4%です。短期証の発行件数は7月8日時点で1,890件です。15区で短期証が発行されました。港区は、16人の対象者がいますが、短期証は発行しませんでした。命に関わる保険証を取り上げるなとの私たちの要求が受け入れられたことは評価したいと思います。
老人保険制度では、高齢者から保険証を取り上げてはならないとなっていたわけですから、後期高齢者医療制度でも短期証の発行はやめるよう広域連合に申し入れるべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、短期証の発行はやめるよう広域連合に申し入れることについてのお尋ねです。
東京都後期高齢者医療広域連合では、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の規定に基づき、各区市町村から依頼のあった場合にのみ、短期証を交付しております。
港区では、きめ細かい納付相談を行うこととし、短期証の発行は依頼しておりません。
こうしたことから、広域連合に対して短期証の発行をやめるよう申し入れることは考えておりません。
3、介護保険制度について
介護保険制度について質問します。
介護保険導入から10年がたちました。特養ホームの待機者増、改悪された介護認定でサービスが受けられない、高額な保険料と利用料の負担増、介護事業者や介護労働者の経営や処遇問題など多くの問題が指摘されています。
日本共産党の国会議員団は2010年5月に全国の介護事業所や地方自治体を対象に「アンケート」調査を行いました。
調査結果でも重い負担を理由にサービスの回数や時間を減らしているとの回答が76.2%。要介護認定については実態を反映していないが83.6%と、問題点が明らかになっています。保険者である自治体からは低所得者を対象にした独自軽減策に取り組んでいるとの回答が多数あり、「国の責任において低所得者に対する保険料・利用料の軽減制度を講じてほしい」と言った要望も多くの自治体から出されました。
厚生労働省は、2012年度の介護保険法の改正に向け介護保険部会の議論をスタートさせ、11月下旬までには「制度見直しの基本的な考え方のまとめ」を公表、2011年度中に国会で成立させる方向です。
この中では、ホームヘルパーがおこなっている生活援助や、要支援Ⅰ・Ⅱまたは要介護Ⅰ程度の人を介護保険制度から切り離す方向、利用者負担を引き上げる方向などが検討されています。財政削減ねらいのこうした改悪を許さないために、私たちも全力で取り組む決意です。と同時に保険者である自治体からも声を上げることが重要です。
制度見直しの検討が始まった今、区として問題点を整理し、「介護保険白書」などで国に対し意見を出すべきです。答弁を求めます。
【答弁】次に、介護保険制度についてのお尋ねです。
まず、制度見直しのため国に対し意見を出すことについてです。
利用者本位の介護保険制度の実現のため、国に対し意見を出していくことは、保険者としての役割として重要です。
区はこれまでも、「介護保険白書」の発行や特別区長会などを通じ、機会を捉え国に対して提言をしてまいりました。
制度を運営していく中で顕在化している課題や、今年度実施する保健福祉基礎調査などにより明らかになっていく課題については整理し、介護保険制度が改善されるよう、今後も必要に応じ、保険者として国に対し提言してまいります。
区として、
①一般財源を投入して保険料の軽減を図るべきです。
②利用者負担の軽減のために、非課税者を対象に行っている、訪問介護や訪問看護への3%負担を他の在宅サービスにも拡大すべきです。
③7月末の特養ホームの入所申込者は360名です。待機者をなくすためにも、早急に特養ホームの建設計画急ぐべきです。その際、多床室を併設すべきです。答弁を求めます
【答弁】次に、一般財源の投入による保険料軽減についてのお尋ねです。
介護保険制度では、介護サービスを賄う財源を、保険料と公費によって一定の割合で負担することが、介護保険法及び介護保険法施行令で定められております。
区の一般財源を投入して、第1号被保険者保険料を軽減することは、介護保険の財源構成を崩し、給付と負担の関係を不明確にすることになります。
したがいまして、一般財源を投入して、保険料を軽減することは適当ではないと考えております。
次に、区独自の利用者負担軽減策の拡大についてのお尋ねです。
区独自の利用者負担軽減策をさらに拡大することについては、サービスを利用する区民と利用しない区民との負担の公平性などから、課題も多いと認識しております。
従いまして、区独自の軽減策の拡大については、現時点では考えておりません。
次に、特別養護老人ホームの建設についてのお尋ねです。
区は、平成22年3月「ありすの杜南麻布」に200床の特別養護老人ホームを整備したことにより、合計711床のベッドを確保したところです。これにより、23区で一番の整備率となりました。
今後の特別養護老人ホームの建設計画につきましては、要介護認定者数の推移を見定め、ありすの杜の入所希望者の分析、保健福祉基礎調査の結果等を踏まえ、グループホーム、ケアハウス等住居系施設の整備の必要性も合わせて検討してまいります。
これらの結果を踏まえ、低所得者の方への対応も含めた、高齢者の多様な住まいについて、地域保健福祉計画改定の中で検討してまいります。
【再質問要旨】特別養護老人ホームの建設計画を推進するべき。
【再答弁要旨】高齢者の方々が住みなれた地域で安心して暮らすことができるためには、特別養護老人ホームの整備だけでなく、在宅サービスや施設サービスを総合的に推進していくことが必要だと考える。
4、総合的な熱中症対策について
次に総合的な熱中症対策について質問します。
先日、77才の区民から手紙が届きました。
「病院で診察を受けた際、担当の先生が「エアコンを入れた方がいいのでは、でも電気代が高いからね」とおっしゃってました。冬は生活保護の手当が出ますが夏はないので、7・8月の2ヶ月だけでも出していただけたら水分の補給と風だけで過ごす苦痛から逃れられると思います。老人が熱中症で亡くなるニュースが連日でていて、暑さをガマンしていたために命を落としたのかと苦痛を感じます。連日35度は普通の人でも苦しいので、何とか対策をたてていただけないでしょうか。戦争の時、小学生でした。空腹と空襲の中、生き残った今、地獄の苦しみを又味わっています。助けて下さい。」同封されたメモ紙には7月8月の毎日の室内の温度が書かれています。34度、35度が続いています。中には37度の日もあります。切実な手紙です。区長の元にも届いていると思います。
今年の夏は連日の猛暑日で、8月に熱中症で救急搬送された人は全国で28,269人(総務省消防庁集計)。2008年の集計開始以来最悪で、昨年の4倍以上、うち65歳以上の高齢者が約50パーセントを占めました。
東京都観察医務院の集計では23区で、梅雨明け(7月17日)から9月6日までに136人が亡くなり戦後最悪を記録。65才以上は118人で86.7%。一人暮しが圧倒的に多く、熱中症になりにくいと思われがちな屋内での死者がほとんどを占め、約60%の方がクーラーを設置していませんでした。
反貧困ネットワーク事務局長の湯浅誠さんは、「猛暑による被害といえば、いかにも天災であり、万人に等しく襲いかかるような印象を与える。しかし、実際には猛暑で倒れるのは高齢者や低所得者といった社会的弱者が多い。月の食費を2万円程度に押さえ込まざるを得ない低年金・低所得者世帯にとって、気兼ねなくクーラーを使うことによる月額5,000円から7,000円の電気代は、1週間から10日間の食費を意味する。食費を削るか、電気代を削るかという究極の選択だが、いずれにしろ体力の消耗は避けられない」と指摘しています。
私たちには、ほかにも対策を求める声が寄せられています。「クーラーを付けたくてもお金がない」、「電気代は極力節約しないと払えなくなる」、「地震と同じ天災だ。でも避難するところもない」、「戸や窓を1日中開けっ放しでジッと我慢しても限界もある」と、まさに命に関わる問題です。 総合的に熱中症対策をとるべきです。
①注意報・警報が行なえるよう熱中症警戒システムを実施すること。
②携帯用熱中症計やクールスカーフなどを独居高齢者に配り予防知識の普及・啓発を強めること。
③生活保護受給者や低所得者にクーラー設置費、電気代の助成をすること。
④生活保護の「夏季加算」を国の制度として創設するよう求めること。
⑤区有施設での緊急避難場所を決めること。
⑥区の訪問活動の強化と、NPOなどの民間の活動への財政支援を行なうこと。
答弁を求めます。
【答弁】(1)熱中症警戒システムの実施について
総合的な熱中症対策についてのお尋ねです。
熱中症警戒システムの実施についてです。
区は、熱中症に関する正しい知識の普及と予防に向けて、広報みなと7月21号や区のホームページ等で、環境省の熱中症予防のホームページの紹介などを通じて啓発に努めております。
また、注意報や警報につきましては、日本気象協会や環境省が毎日、熱中症予防情報を提供しており、こうした情報は、新聞やテレビ等の報道により広く周知されております。
今後、熱中症予防の効果的かつきめ細かな情報提供のあり方について検討してまいります。
(2)ひとり暮らし高齢者に対する予防知識の普及啓発の強化について
次に、総合的な熱中症対策についてのお尋ねです。
まず、ひとり暮らし高齢者に対する予防知識の普及啓発の強化についてです。
この夏の、ひとり暮らし高齢者等への熱中症予防対策としては、総合支所のケースワーカーや保健師、地域包括支援センターの職員が訪問の際に、予防のポイントを記載したチラシを配布するなど注意を喚起してまいりました。
このチラシは、配食サービスの利用者に対しても、事業者を通じて配布いたしました。
また、居宅介護支援事業者や訪問介護事業者へ、サービス利用者へのチラシの配布と注意喚起を依頼いたしました。
さらに、福祉会館や地域包括支援センターなど区内の施設へも送付し、利用者へ注意喚起をいたしました。
今後とも、熱中症対策の普及、啓発に努めてまいります。
クールスカーフ等の配布につきましては、考えておりません。
(3)生活保護受給者や低所得者にクーラー設置費、電気代を助成することについて
次に、生活保護受給者や低所得者にクーラー設置費、電気代を助成することについてのお尋ねです。
生活保護受給者や低所得者に対して、区独自にクーラーの購入や設置に要する費用、また、使用に係る電気代の助成を行なうことは考えておりません。
なお、生活保護受給者に対しては、この夏に行なった定期訪問の際、熱中症対策のチラシを配布するなど注意を喚起してまいりました。今後も様々な機会を通じて予防知識の普及、啓発に努めてまいります。
(4)生活保護の「夏季加算」の創設を国に求めることについて
次に、生活保護の「夏季加算」の創設を国に求めることについてのお尋ねです。
先般、夏季加算の新設について、厚生労働大臣から「検討していきたい」との発言があったと聞いております。
今後、国において生活保護制度全体との関連性も含め、夏季加算の新設が検討されていくものと認識しておりますので、その動向を見守ってまいります。
(5)緊急避難場所を決めることについて
次に、緊急避難場所を決めることについてのお尋ねです。
区としては、区有施設を熱中症対策の緊急避難場所とすることにつきましては、様々な課題があると認識しており、今後、調査・研究をしてまいります。
(6)訪問活動の強化等について
次に、訪問活動の強化等についてのお尋ねです。
現在、総合支所にケースワーカーと保健師を配置し、地域の高齢者の相談や訪問活動を行っております。
地域包括支援センターでは、高齢者支援の拠点として、高齢者を訪問しております。
ケースワーカーや保健師、地域包括支援センター職員は、訪問の際、高齢者の様子を確認しながら積極的な声掛けを行っており、熱中症対策のチラシを配布するなど、注意を喚起してまいりました。
この夏の猛暑の際には、高齢者が住む集合住宅の自治会から連絡を受けた地域包括支援センター職員が訪問し、脱水症状の高齢者を救助した例もあります。
今後とも、高齢者などの安全安心を図るため、訪問活動の強化に努めてまいります。
NPOなど民間の活動への財政支援については、その活動内容の把握に努めてまいります。
5、白金6丁目の建築問題について
白金6丁目の建築問題について質問します。
白金6丁目の建築紛争で、9月8日、建築主である新日鐵開発は、「工事妨害禁止の仮処分申立書」を東京地裁に申請しました。住環境を守ろうとする住民と区民に対する暴挙です。
住民は「住環境を守れ」と、1年以上にわたり地域ぐるみで運動をすすめています。
この間、建築主側は住民からの質問にはまともに答えないどころか、工事説明も行わず、工事協定書も結ばず、区の指導も無視し、7月14日に資材搬入を強行しようとしました。一方的に迷惑・被害を受ける住民は当然のように、新日鐵側に抗議を行ない、同時に話し合いの開催を強く求めているにもかかわらず、連日のように搬入行為を繰り返すため、住民はその都度やむをえず抗議をつづけてきました。それを「妨害」として訴えるなど、とんでもありません。
6月議会での我が党の質問に対し、副区長は「条例では建築主は周辺の生活環境への十分な配慮と良好な近隣関係を損なわないよう勤めなければならないとしています。住民側の理解を得た上で工事に着工するよう指導する」と答弁しました。
改めて、紛争を条例の立場で解決するために、新日鐵は工事を直ちに中止し、住民との話し合いに応じるべきであり、区は強く指導すべきです。
答弁を求めます。
【答弁】次に、白金六丁目の建築問題についてのお尋ねです。
区は、これまでも、事業主に対して、円満な話し合いを行い、近隣住民の理解を得るとともに、工事協定書締結後に工事着手するよう指導してまいりました。
また、区において近隣住民の方々と建築主との話し合いを数回にわたり開催し、円満解決に向け取り組んでまいりました。
しかしながら、その後の状況は、ご指摘のとおり、解決には至っておりません。
引き続き、条例に基づき、話し合いや説明会を重ね、住民の理解を得た上で工事に着手するよう、建築主等を強く指導してまいります。
最後に、東麻布2丁目に(株)大京が計画しているワンルームマンションについて質問します。
この計画は、4月27日(火)に住民に説明されました。計画説明の途中で、直近で解体工事が行われることが判明し、後半は解体工事の説明になっています。この説明を受けて、住民のみなさんは、「紛争予防条例に基づく説明会は、途中で解体工事説明になり、計画そのものの説明会は終了していない」ことを、建築課長と紛争調整担当に陳情。その後、署名を集め計画変更を求める陳情書を区長に提出しています。
解体工事でも、散水が不十分、騒音が基準値を超え、東京都と港区の環境課の指導がはいると言った状況で、その都度、事業者の誠意のない対応について、陳情を繰り返してきました。
しかしながら事業者は、説明が途中にもかかわらず、条例上の説明会報告書を5月17日に提出。
住民が説明会は不十分で、「条例上の説明会」は終わっていないと再三陳情していたにもかかわらず、区は「書類が整っていれば受けざるを得ない」と住民には知らされないまま報告書を受理。建築確認申請の手続きが進められました。
住民はこうした区のやり方にも大きな怒りを持っています。
建築に対し素人の住民にとって、ある日突然、住環境に大きな影響が出る計画が持ち上がったときに、頼りになるのが紛争予防条例であり、それを所管している建築課です。
ところが今回のように、陳情に行っても、陳情書を提出しても、「書類が整っていれば受理せざるを得ない」となれば、事業者はとりあえず資料を配って、一通り説明すれば、それで手続きが進められる。これでは、紛争予防条例はただ単に手続きを進めるための条例でしかありません。
8月6日の説明会は、「確認が降りた計画の工事説明を行います」と住民に通知し、住民対策会社が、一方的にまくし立て、住民の怒りを買いました。
委託を受けたというキャストユーデイの担当者は、自己紹介もないまま話を進め、「聞こえません」との住民に対し「マイクを使っていますから聞こえるはずです」。「チョット待って下さい」には「待てません」と本当にひどい対応でした。
< この説明会を受けて、区役所で8月26日に話し合いが行われましたが、この場でも高さや容積など計画そのものに対しては変更できないと、最初から住民の意見を聞かない態度に終始。翌27日の夕方から夜にかけて30日の工事説明会のチラシを配布、住民が「その日は町会の集まりがあって参加できない」と日時の変更をお願いしても応じず、31日の夜9時30分過ぎに「明日から着工します」とのお知らせを配布するというまったくひどいやり方です。白金の例でも指摘したように、紛争予防条例に基づく指導になっていないのが現状です。
①本来の紛争予防条例の目的に添った指導を行うよう改善すること
②紛争予防条例の7条に基づく説明会報告書については、形式が整っていたら、受理せざるを得ないとの立場でなく、条例の目的に沿った説明会が行われているかきちんと検証し受理を決定すること。
③紛争状況が激化し、区役所の主催で話し合いが行われる際は、必ず複数の職員で担当すること
④紛争状況になった現場については、担当者はきちんと現場を確認すること。その体制がとれないというのであれば体制強化を図ること。
⑤今回の住民対策会社などが強行に説明会を開催することのないよう、事業主、工事施工業者による説明会を開催するよう指導すること
⑥区は事業主(大京)に対し、周辺環境への配慮と、改めて住民の理解を得,円満な話し合いが出来るよう指導を行うこと。工事着工に当たっては、住民の理解を得た上で工事協定書を結ぶよう指導すること。
答弁を求めます。
【答弁】(1)本来の紛争予防条例の目的に沿った指導を行うことについて
次に、東麻布二丁目のワンルームマンション計画についてのお尋ねです。
まず、本来の紛争予防条例の目的に沿った指導を行うことについてです。
区は、これまでも、いわゆる紛争予防条例に則して、近隣の皆様や建築主の互譲の精神による協力を得ながら、建築紛争の未然防止や解決に努めてまいりました。
今後も、良好な近隣関係の保持と地域における健全な生活環境の維持及び向上に資するという、条例の目的に沿い、より一層、指導を徹底してまいります。
(2)説明会報告書の受理のあり方について
次に、説明会報告書の受理のあり方についてのお尋ねです。
説明会等の開催方法や説明会で周知すべき事項は、紛争予防条例及び条例施行規則に規定されております。
区では、条例及び規則に基づき適切に説明がなされたか、また、質問に対して丁寧な回答がなされたか等を精査・確認し、説明会等報告書を受理することとしております。
今後とも、住民の皆様に分かりやすい丁寧な説明が行われているかを議事録により確認するなど、説明会等報告書の受理にあたりましては、厳格かつ適切に対応してまいります。
(3)区主催の話し合いは複数の職員が担当することについて
次に、区主催の話し合いは複数の職員が担当することについてのお尋ねです。
近隣住民の方々と建築主双方の了解の下、区が主催する話し合いは、建築紛争調整を担当する職員が、関係者との連絡・調整、当日の進行管理などを行い、円満な運営に務めております。
今後は、参加人数などの状況に応じ、複数の職員が対応することも考慮してまいります。
(4)担当者の現場確認の励行について
次に、担当者の現場確認の励行についてのお尋ねです。
建築紛争がどのような地域状況や周辺環境の下で発生しているかを把握することは、建築紛争を防止し、解決する上で必要なことです。
これまでも、極力現場を確認してまいりましたが、今後は、陳情や相談の有る現場につきましては、確認を行うよう努めて壷いります。
(5)事業主、工事施工業者による説明会開催の指導について
次に、事業主、工事施工業者による説明会開催の指導についてのお尋ねです。
区は、紛争予防条例において、説明会に建築主が出席することを義務付けるとともに、説明会等の後も話し合う機会を設けることを建築主と工事施工者に求めております。
説明会等が近隣対策を請け負う会社のみで行われた事例は無いと承知しておりますが、今後も、建築主や工事施工者が主体となって近隣住民への説明会や話し合いを開催し、運営するよう指導してまいります。
(6)区が事業主を適切に指導することについて
最後に、区が事業主を適切に指導することについてのお尋ねです。
区は、これまでも、事業主に対して、円満な話し合いを行い、近隣住民の理解を得るよう指導してまいりました。引き続き、工事着手につきましては、工事協定書締結後とするよう指導してまいります。
【再質問要旨】
説明会報告書の受理については、条例の目的の沿った説明会がおこなわれているか検証のうえ受理すべき。
【再答弁要旨】
説明会等報告書の受理にあたっては、質疑応答の正確な記載を求めるとともに、近隣関係図、作業方法、危害防止等の説明が適切に行われたかを確認し、記載漏れがある場合は修正資料の追加等指導している。今後とも、適切な説明をするよう指導するとともに、厳格な内容確認を行う。
以 上