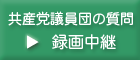9月に、東京都住宅政策審議会から「東京におけるマンション施策の新たな展開について」の答申が出されました。
「都内のマンションストックの約2割が、1981年以前の旧耐震基準で建築されており、その多くは耐震不足が懸念されている。また、今後、高経年化と居住者の高齢化を合わせたマンションにおける「二つの老い」が進んでいくため、今のうちから中長期的な視点に立って、マンションの適正な維持管理の促進や、老朽化したマンションの円滑な再生を図る施策を先行的、計画的に講じていく必要がある。都が率先して諸課題に取り組み、都民の豊かな住生活を支える安全で良質なマンションストックを形成し、将来世代に継承していくことが求められている。」と述べています。
区民の約9割がマンションに居住している港区でこそ率先して取り組んでいくべき課題です。
2011年の「港区分譲マンション実態調査報告書」では区内の4割(528棟)が旧耐震基準となっています。区では分譲マンション耐震化支援事業、耐震診断助成、耐震化促進事業などを進めてきたものの助成を受けて耐震診断を行ったのは150棟(28,4%)であり、そのうち135棟(90%)が耐震補強が必要なIS値0,6未満です。さらに倒壊危険性が高いとされる0,3を下回るものが40棟(27%)もありますが、助成を受けて耐震改修工事を行ったのは17棟だけです。現在、耐震補強工事を実施している区内にある100戸のマンションの事例では、住民合意、 耐震補強計画、事業者選定、 資金計画、実施計画など多くの課題があり、耐震改修計画委員会を発足してから工事着工まで2年半を要しています。粘り強い取り組みと専門家のアドバイスや改修工事費助成などがなければたどり着けないのが実情です。
耐震化の促進を図るため、 ① 耐震診断、耐震改修に関する助成制度のいっそうの周知を図ること ② 改修工事例について可能な限り課題解決への経験を普及すること ③耐震アドバイザー派遣は回数で区切るのでなく、改修工事の見通しが立つまで行うこと 等を求めます 。
旧耐震基準のマンション居住者には、地震が来るたび不安を感じている方も少なくありませんが、耐震化改修実施までには多くの困難があります。切迫性が指摘される首都直下地震への対応が求められているなかで、 経済的なゆとりがない高齢者世帯向けに必要最小限の施工で可能となる部分改修やシェルターの設置が進められています。品川区ではシェルター設置費助成が行われています。区でも高齢者、障害者など災害弱者にシェルターの設置費助成、部分改修助成を行うべきです。 ( 15 4定 大滝議員 )