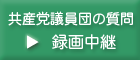私たちは、1月27日に住宅リフォーム助成制度実施を野村副区長に申し入れました。深刻な経済危機のもとで、区内の中小業者の経営と地域経済をどう守るかが重要な課題となっています。全国では数年前から、地元業者に住宅リフォームを発注した住民に費用の一定割合を助成する「住宅リフォーム助成制度」を実施する自治体が広がっています。全国商工団体連合会の昨年11月末時点の調査では、175の自治体で実施されています。工事を地元の中小・零細建築業者に発注するため、「建設不況」で仕事が減って困っている業者からどこでも歓迎されています。地域経済も活性化させます。住民からも「この機会に思い切って家をリフォームしたい」と歓迎され、申請の動きが広がっています。港区でも是非事業化すべきです。その際、区内の住宅事情を考慮して、マンションのリフォームも対象にすることが大切です。まず、全国の進んだ自治体の実態把握を速やかに行い、遅くとも来年度中の実施となるよう急いで事業化をすべきです。 (11 1定 星野議員 代表質問)
景気対応緊急保証制度は、業況が悪化した業種の中小企業に対し、民間金融機関からの融資を信用保証協会が100%保証する制度です。 菅内閣は中小事業者にとって命綱ともいえる、この制度を3月末で打ち切り、それに伴う激減緩和措置を4月から半年間実施すると発表しました。2010年2月から中小企業の全業種、82事業種を対象として実施してきましたが、対象業種を20業種まで縮小します。これでは減少する業種数があまりにも大きいため、政府は激減緩和と称する手立てで新年度をスタートせざるをえなくなったのです。しかし、激減緩和措置でも対象となるのは48業種、現行の58.5%にすぎません。中小零細事業者が借りられる緊急保証制度は絶対に必要です。全国市長会では「期間の延長」と「さらなる拡充」を要望しています。激減緩和措置を実施するので、推移を見守るなどと悠長なことを言っている間に、倒産したらどう責任をとるのか。しっかりと継続するよう国に意見をいうべきです。 (11 1定 星野議員 代表質問)
中小企業の倒産件数は、ここ数年高い水準で推移しています。長引く不況の下、円高によって、区の経済を支えている中小企業は、苦境に追い込まれ、「仕事は激減、このままでは倒産する」という悲痛な声が更に広がっています。特に、仕事がなくても支払い続けなければならない工場家賃、リース料、電気基本料などが中小零細の製造業者の経営を圧迫しています。京都市では来年度から、一部中小企業を対象に実施している機械のリース代補助事業を、全ての中小製造企業に拡大し、支援を強めています。区に工場家賃、リース料など固定費の直接補助制度を緊急に創設すべきです。 (11 1定 星野議員 代表質問)
五之橋は1997年に補修工事が行われましたが、区民が要望していた拡幅は行われませんでした。五之橋は買い物、通院、散歩、食事など区民の日常生活に欠かせない橋です。平成24年度から古川地下調整池取水施設工事が五之橋近くの一画で始まる計画で、危険な状態のまま多くの工事車両が五之橋を通行することになります。五の橋の架け替えを早期に行うこと。また、調整池取水施設工事の期間中は、歩行者・自転車通路を充分確保し車道とは分離することを要求します。 (11 1定 星野議員 代表質問)
政府は現行の公的な保育制度を解体する新システムを検討して、今国会への法案提出を狙っています。現行制度では市町村が保育の実施義務を負っていますが、その義務をなくし、保育サービスの実施を市場任せにするものです。新システムが、これまでの保育制度と大きく異なる点として、①市町村の責任が後退し、利用者と保育所などとの直接契約になる、②保育料が、所得に応じた負担から、利用した長さに応じた「応益負担」になる―こと等が今国会でも明らかになりました。市町村の役割は、「空き情報を紹介するだけの不動産業者のようなものになる」とも指摘されました。政府の示す案では、保護者は市町村から、就労時間に応じて保育所を利用できる時間の認定を受けます。認定されても、保育所が足りなければ入ることはできません。また、認定時間を超えて子どもを預ける場合、非常に高額な保育料になる恐れがあります。お金がない人は排除されかねません。国と地方自治体の責任を放棄し、子どもをもうけの対象にする新システムの検討は中止するよう国に求めるべきです。 (11 1定 星野議員 代表質問)
認可保育園に入所できない子どもは、高い保育料で認証保育所か無認可保育園に入所するしかありません。無認可保育所は補助がなく、「月13万円もかかり、負担が大変」など、切実な訴えが寄せられています。無認可保育園保護者への保育料助成を行うべきです。また、認証保育所保育料補助金は、補助区分を細分化し引き上げるべきです。 (11 1定 星野議員 代表質問)