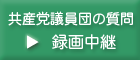毒性が強く、吸い込むと肺がんや中皮腫を引き起こすことから、悪魔の鉱物といわれるのがアスベストです。港区は、東京2020オリンピック・パラリンピック大会を前に建設ブームの再来が予想されます。また再開発が目白押しですから、それに伴う解体が発生するたびに近隣住民、通行人、来訪者、現場労働者、検査に行く職員の生命と健康を守る対策は一刻の猶予もなりません。具体的には、
①環境課の体制、環境指導・環境アセスメント担当を抜本的に強化すること。
②川崎市など先進的自治体にならい、周辺住民の方、工事発注者向けの「解体工事についてよく知っていただくためにーアスベスト除去工事等の規制のあらまし」のパンフレットを作成すること。
③石綿含有成形板50㎡以上の建築物の解体については、大気中のアスベスト濃度の測定を義務づけるこ
④石綿含有成形板を使用している場合は「手作業で取り外す、または十分な散水により粉塵が飛散しないように努める」と努力義務です。川崎市のように、きちんとした除去を義務づけること。
⑤簡単にアスベストの含有が測定できる携帯用アスベストアナライザ-を購入すること。
⑥アスベストの飛散濃度を測定できる繊維状粒子自動測定器リアルタイムファイバーモニタ-を購入すること。⑦石綿の実態調査の専門家を養成する「建築物石綿含有建材調査者制度」、区の責任で資格取得をすすめること。
以上求めます。 (16 2定 熊田議員)