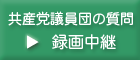非正規雇用が急増し、3人に1人が不安定雇用、若者は2人に1人が派遣です。マスコミではワーキングプアが何度も特集されるなど社会問題になり、「日雇い派遣の禁止」を厚生労働大臣が公言するなど、変化も生まれています。区長も、施政方針演説で、「定職をもてない若者の社会問題化など、日本全体が閉塞感に包まれているかのような社会経済状況が生まれている」と指摘しているのですから、国に対して、「日雇い派遣の即刻禁止」を含む「労働者派遣法」の抜本的改正を求めるべきです。(08 2定 沖島えみ子 一般質問 )
後期高齢者医療制度の廃止は、4年後に先送りされ、厚生労働省は75歳で区分した現行制度に変わる素案をまとめましたが、素案によると65歳以上は原則として国保に加入し、現役世代とは分けて、医療の実態にあわせ、応分の負担を求める。保険料の設定は各都道府県単位で2013年の実施をねらっています。結局75歳を65歳に引き下げただけで制度の内容は後期高齢者と全く変わりなく、大問題です。後期高齢者医療制度廃止を掲げた民主党の責任が大きく問われています。後期高齢者医療制度は廃止するよう国に求めるべきです。(10 1定 風見利男 代表質問)
東京都は「都立病院改革」と称し、16あった都立病院を半分に減らし、広尾病院は独立行政法人化しようとしている。独立行政法人化されれば、小児科や精神科など不採算部門が切り捨てられる心配があり、分娩料や個室料などが引き上げられ、都民が安心して病院にかかれなくなることが予想される。患者や働く人に不安を与える独立行政法人ではなく、都立広尾病院を、引き続き都立病院として存続するよう、東京都に強く申し入れるべき。(09 2定 大滝実 代表質問 )
事業を実施するには、医療上、生活上の相談に応じるために医療ソーシャルワーカーを置き、かつ、そのために必要な施設を備えるなど、いくつもの基準をクリアーしなければなりません。実施主体は医療機関ですが、許認可権は都道府県にあります。税制上、固定資産税の減免という優遇はありますが、医療費は医療機関の負担となります。多くの医療機関で実施できるよう、国や都に対し支援策の充実・拡充を求めるべきです(09 1定 沖島えみ子 代表質問 )
社会福祉法では「生計困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う事業」や「...無料または低額な費用で、...介護老人施設を利用させる事業」を定めている。医療では無料低額診療制度として事業化され、病院や診療所が実施主体になる。患者さんは、区の窓口(芝地区総合支所:くらし応援課保健福祉係)に相談し、病院が発行している特別診療券を受け、医療費が免除・減額される。港区内では、済生会病院、愛育病院、東京掖済会クリニックがこの事業を実施している。 こういう制度があることを区民に知らせるべきだ。また、区の窓口を、各総合支所に拡大すべきだ。(09 1定 沖島えみ子 代表質問)
区は滞納者に「分納」の相談に応じているといいますが、窓口では、「滞納額の半分以上を払わなければ保険証を発行しない」といわれた方がいます。保険料を滞納せざるを得ない生活困窮者が、滞納額の半分を一括で納入するのは、極めて困難です。区民の命と健康を守る立場から、保険料を納付する意思のある人には短期保健証を発行するよう、窓口対応の改善も含め、要綱を改めるべきです。(09 1定 沖島えみ子 代表質問 )
特別養護老人ホームは定員200に対し569人で2.8倍の申請。ケアハウス自立型は定員10人に対し46人で4、6倍。介護付きが38人に対し96人で2、5倍。認知症グループホームは18に対し53人で2、9倍。どれだけ多くの区民が施設入所を希望しているか、この状況からも明らか。老老介護や在宅介護が長期になり家族介護ではもう限界と感じている方、経管栄養や気管切開など医療的処置が必要なため、どんなに介護度が高くてもショートステイも利用できずにいる方など、在宅介護の現場は大変深刻。次の保険福祉計画まちでなく、高齢者施設建設計画を早期に作るべき。(10 1定 風見利男 代表質問)
生活保護における母子加算、老齢加算の復活について 母子加算の復活は当然のことであり、来年度以降も継続すべき。その財源確保に、国民のための施策の削減はやめるよう、国に求めるべき。(09 4定 熊田ちづ子 代表質問 )
特養ホーム白金の森の大規模改修について ①入居者、デイサービス、ショートステイ利用者と家族などへの充分な説明を行い、意見をよく聞き、個人個人に則した充分な対応を行なうこと。②利用者への負担を最低限度にする計画を緻密に作ること。③デイサービスについては仮設場所を確保すること。④事業縮小で事業者の収入減の場合は区として支援をすべきこと。を要求します。(09 4定 熊田ちづ子 代表質問)
南麻布に建設中のケアハウスは、使用料が高すぎて、高額所得者でなければ入居できない。ケアハウスの使用料の設定については、どんな収入階層の人でも日常生活に最低必要なお金が手元に残るような仕組みにすること。とりわけ所得の低い人たちでも入居できるような支援策を検討すべき。(09 4定 熊田ちづ子 代表質問 )
「福祉施設 桜川」は、特別養護老人ホーム、障害者の通所・入所施設、老健施設を運営する港区で初めての、区有地を活用しての民設・民営施設です。この間、私どもに特養ホーム「桜の園」や、老健施設「バラの園」についての、苦情や問い合わせがありました。施設全体として、運営やサービス提供、また、利用者や職員からの苦情・問い合わせに、どのように対応しているのか、まず、実態を充分に聴き取るべきではないか。その際、施設側の聴き取りだけにせずに、利用者と職員からも直接聞き取ること。アンケート方式での意見聴取なども工夫しながら、より実態が掌握できるようにすること。
さらに、区内の特養ホームなどの福祉施設について、利用者からどんな苦情や要望があるのか、それへの対応が適切かなど、区が詳細に実態をつかめる仕組み、ルールを確立すべきです。(09 2定 星野たかし 一般質問 )
荒川区では、特養ホームなどの介護施設の食費・居住費の有料化(2005年)で、負担に耐えられない世帯があるため、7月から負担を軽減します。課税世帯で年収500万円以下(特例4段階)の人の負担を、4人部屋で1万5千円程度減額。グループホーム・小規模多機能型施設も一部を軽減します。本来は、低所得者については居住費・食費を無料にすべきですが、当面の対策として、港区でも、本人が非課税の場合、特例4段階の人については、特養ホームの居住費・食費の負担軽減を図るべきです。(09 2定 星野たかし 一般質問)
特別養護老人ホーム建設には、多額のお金がかかります。 国や都に次の要請を行うよう求めます。国や都は、特養ホームなどの高齢者施設建設のための用地の無償譲渡や、無償貸与を行うこと。小規模施設に限定せず、建設費補助を行なうこと。実態に見合った補助金額とすること。その際、多床室も補助対象とすること。(09 2定 星野たかし 一般質問)
国は、個室やユニットタイプの特養ホーム建設以外には、補助金を出さないことを決めました。また、ホテルコストと称して部屋代を徴収するため、お金のない人は入所できません。また、ユニットタイプには生活保護者は入れません。現在、建設を進めている、南麻布の特養ホームの一部を、多床室に変更するように、早急に検討すべきです。また、今後は、必ず多床室も含めた計画とすべきです。(09 2定 星野たかし 一般質問)
芝公園のなかには、夏はプール、それ以外はフットサル場という、きわめてユニークな港区立芝公園多目的運動施設があります。都の野球場、テニス場も含めた統一的な管理をするのが理想的ではないか。早期に都の施設の区移管が実現するよう、東京都に強力に働きかけるべきです。(10 1定 風見利男 代表質問 )
文部科学省は、一学級あたりの標準的な児童生徒数を「40人」と定めた国の基準について、人数を減らす方針を固め、早ければ2011年度から数年かけて完全実施することを想定していると報道された。長年の運動と日本共産党議員団の粘り強い質問の中で、遅ればせながら東京都も少人数学級への第一歩を踏み出した。港区教育委員会は、東京都の少人数学級の方針通りに実行すること。あわせて、港区独自で実施している補助教員の配置を継続すること。(10 1定 風見利男 代表質問 )
新政権は来年度から、全国学力テストについて抽出方式で行うことにしましたが、抽出率を40%と高くするなど、気がかりな点を残しています。せっかく見直しするわけですから、教育関係者の意見を十分聞き、抽出の割合、抽出する自治体を限定するなど十分な検討を行うよう、国に要請すべきです。(09 4定 いのくま正一 一般質問)
新郷土資料館設置構想は、15年以上前から検討され、前基本計画では、2008年度までに設置予定でした。ところが、未だ用地も確定していません。区内には多くの区有地、公有地があります。一刻も早く土地選定を具体化すべきです。また新資料館が設置されるまで、特別展などをもっと増やすなどし、所蔵資料を公開すべきです。(09 4定 いのくま正一 一般質問 )
南青山2丁目にあった都営住宅が廃止となり、現在更地になっています。東京都から、取得するなどして(無償譲渡、無償貸付、低価格での取得など)、区民が気軽にスポーツに取り組むことができる施設を建設すべきです。
(09 3定 風見利男 代表質問 )
給付型奨学金制度がない国は、OECD加盟30カ国のなかでメキシコ、アイスランド、日本の3カ国だけです。経済的な理由で進学できなかったり、中途退学を迫られることがないよう、給付型奨学金制度を創設すべきです。早急に給付型奨学金制度を実施するよう、国に要求すべきです。(09 3定 風見利男 代表質問 )
土地代や家賃などが高い港区。土地代を含めた建設費補助を実態にあったものにするよう、国や東京都に求めるべきです。(09 1定 沖島えみ子 代表質問 )
公私立高等学校授業料の減免制度の創設、返済なしの奨学金制度の創設、滞納を理由にした退学や除籍でなく、延納などの手をつくす、通学費補助など、きめ細やかな制度をつくるよう、国に働きかけるべきです。 国の制度が改善・充実されるまでの間、港区の奨学金制度の常時受付を行うべきです。 卒業した方については、返済を免除すべきです。(09 2定 星野たかし 一般質問)
小中一貫校について、港区基本計画で来年度、朝日中通学区域、港陽中通学区域で調査を行ない、2010年度に港陽中通学区域で実施、朝日中通学区域で設計を始めるとしている。区民が知らないうちに突然基本計画に具体化され、地域住民や学校関係者は、あまりにも拙速な計画で、驚きと大きな疑問をいだいている。子どもたちによりよい教育環境はどうあるべきか、一地域だけの問題とせず、これこそ幅広い区民の論議と合意が必要。保護者、関係者、区民に広く情報提供し、十分な時間をかけ、中止も含め区民的議論を行なうべき。(09 1定 いのくま正一 一般質問 )
学校選択制が導入されてから6年が経過しました。導入前の2002年度と今年度を比較すると、学区域外入学者数は、小学校で1.78倍、中学校では2.19倍と地域離れが進んでいます。東京大学の基礎学力研究開発センターが行なったアンケートでは、公立小・中学校の校長先生の9割が、「学校選択制は、学校間の格差が広がる」「学校への無意味なレッテルづけが生じる」と批判的に答えています。学校選択制を実施してきた自治体が、「地域の連帯感が薄れてきている」などを理由に廃止や見直しを始めています。「地域のつながり」の崩壊を進行させ、学校間の格差を広げる学校選択制は、廃止を含め抜本的に見直すべきです。(09 1定 いのくま正一 一般質問 )
校庭等の芝生化を、機会ある毎に提案し、一部芝生化がすすんでいるが、雨の後すぐに使えないとか、養生が大変等々の理由で、全体的にはなかなか進まない。早急に「鳥取方式」を検討し、せめて学校や広場は裸足で思い切り飛び跳ねることのできる天然芝にすべき。また、東京都の助成制度も積極的に活用すべき。 ( 09 1定 沖島えみ子 代表質問 )
障害者自立支援法によって、障害者が生きるために欠かせない福祉や医療の支援に1割の自己負担を課すのは、生存権を保障した憲法に違反するとして、全国の障害者ら71人が負担取り消しなどを求めた集団訴訟をめぐり、原告・弁護団と国側は1月7日、同法廃止などを定めた基本合意文書を取り交わしました。合意文書は、「国は憲法の理念にもとづき提訴した原告の思いに共感し、これを真摯に受け止める」とし、応益負担の速やかな廃止、2013年8月までの自立支援法の廃止と新法の制定をうたっています。区民の生活とくらし、人間の尊厳を守る立場の区長として、鳩山内閣に対して、約束通り、障害者自立支援法の廃止を求めるべきです。当面、住民税非課税の障害者への「応益負担」をなくすように要求すべきです。(10 1定 風見利男 代表質問 )
私たちは介護施設を訪問・調査し、どの施設も人の確保に苦労している実態を取り上げ区の支援を求めてきました。現場の職員からも、住宅手当を支給するよう求める請願が出されています。この要求と運動を受け、区は保健福祉計画で、特別養護老人ホームなど15施設に月額5万円(特養で5人分)の支給を決めました。ところが、対象施設に障害者の入所施設は含まれていません。早急に、障害者施設も対象とすべきです。(09 1定 沖島えみ子 代表質問)
我が党は、心身障害者福祉手当を精神障害者にも支給するよう質問や条例提案を行ってきました。 ところが区長は、「調査結果をもとに精神に障害のある方の福祉サービス向上に努める、2009年度策定の障害者計画で示す。」と答弁しているが、今回示された精神障害者の新規事業は、福祉売店と福祉喫茶の設置だけです。遅れている精神障害者の施策からも極めて不十分です。早急に、精神障害者も心身障害者福祉手当の対象とすべきです。(09 1定 沖島えみ子 代表質問 )
障害者自立支援法によって導入された応益負担制度によって、原則1割負担が導入されました。障害による困難を支援する制度がなぜ利益なのか、障害者をはじめ多くの関係者から応益負担の廃止を求める声は後を絶たず、国民世論は政府与党を追い込んでいます。区として自立支援法の根本問題である応益負担、事業所への日額報酬を元の月額報酬にもどすよう国に求めるべきです。改善されるまでの間、非課税者の負担を、区が負担すべきです。 ( 09 1定 沖島えみ子 代表質問 )
昨年実施した 「区民アンケート」には、「森ビルの開発は地域の活性化につながらない」「高いビルはいらないのに金を出すとは何事だ」「住民税、所得税、国保料が高すぎて、25年以上港区に住んでいるが家も買えない。無駄づかいはしないでほしい」など、「再開発補助金支出はやめるべき」の声が回答者の85%を占めました。港区は今後6年間で220億円の補助金を出す計画です。このことに区民は怒っています。多くの区民が納得していない再開発補助金はキッパリと中止すべきです。(09 2定 大滝実 代表質問)
東京23区をはじめ全国各地で、内容の違いはあるものの高さ制限が導入されています。 環境破壊を許さず、区民の生命・安全、財産を守るために、区民の声を真正面から受けとめ、区民と相談し絶対高さ制限の導入について、区としての案を早期に示すべきです。(09 2定 大滝実 代表質問 )
5月に港区が公表した「高層住宅の震災対策に関する基本方針」の策定の背景について、区は、「超高層や高層建築物では、地震などの災害が発生した場合、家具類の転倒、ライフラインやエレベーターの停止など、高層住宅特有の様々な問題が生じることにより、自宅における生活が困難になることが予想される。」といっています。現在ある、高層・超高層への対策は当然必要ですが、災害を拡大させ生活困難が生じることが「予想される」と自らいっているのですから、超高層建設推進をこれ以上は止めるべきです。(09 2定 大滝実 代表質問 )
12月の中旬から区民への説明会が区民センター等で行われ、インターネットでも区民意見が募集されました。しかも、地区版計画書や地域保健福祉計画、教育振興プランなど7つの説明会や意見募集も同時期に行われました。年末・年始の忙しい時期に説明会を集中させたことは、「区民は参加しなくても結構」と考えているのか。こうした忙しい時期でも、区民は「これ以上の超高層ビルはいらない」など、積極的な意見や建設的な意見を多数寄せました。こうした多数の区民意見や議会の意見を尊重し、基本計画に反映すべきです。(09 1定 沖島えみ子 代表質問 )
なぜ、「まちづくりマスタープラン」の区民参画に「要綱」を設置しているのに、基本構想に次ぐ基本計画には「区民参画要綱」を設置していないのか。「港区付属機関等の設置および運営に関する基準」第3条 付属機関等の設置の留意点では、(1)専門知識の導入、公正の確保、利害の調整または民意の反映を特に必要とすること、となっています。基本計画は民意の反映が特に必要なはずで、今後は区民が基本計画を作れるようにすべきです。そのために、基本計画策定のための区民参画の要綱を設置し、策定にあたるべきです。(09 1定 沖島えみ子 代表質問 )
区は、基本計画と来年度予算案の説明で、今後6年間で962億円の基金を取り崩す、大規模な施設建設を打ち出しました。962億円の中で一番大きな割合を占めるのが、田町駅東口北地区の整備。同地区に計上された施設の建設費だけで485億円と、素案に盛り込まれた経費の4割を超えます。 スポーツセンターの施設整備費だけでも244億円。豪華スポーツセンター建設が本当に必要なのか、区民の意見を聴くべきです。(09 1定 いのくま正一 一般質問 )
区長は、「市街地再開発事業は防災性の向上」になるとずっと答えています。本当に防災性が向上するのか。中央防災会議の「東南海・南海地震などに関する専門調査会」は12月、巨大地震で生ずるゆっくりとした揺れ、「長周期地震動」の影響を受けやすい、全国の地点の分布を初めて公表。東京地方も影響が出やすいとされています。長周期地震発生時の超高層建築物の安全性が保たれるのかなど、実態調査、影響調査を実施すべきです。 ( 09 1定 いのくま正一 一般質問 )
中小企業を対象に、国の雇用調整助成金に区として独自の上乗せを行うことを求めます。(09 2定 大滝実 代表質問 )
「協働会館」は、1936年竣工の、百畳敷の大広間を持つ近代和風建築であり、唯一都内に現存する戦前の木造見番建築として、建築学的にも民俗学的にも貴重な建物です。東京都と港区の共同で今後の保存・利活用の可能性について、建物の劣化状況調査及び耐震補強調査が実施されました。調査結果の報告会では補強によって安全が保障されることが明らかにされています。都も当面の雨漏り対策を行うための検討を行っているとのことであり、区として東京都に保存・利活用のために改めて強く要求すべきです。(08 2定 沖島えみ子 一般質問 )
米国のオバマ大統領が4月5日プラハで行った演説は、「核兵器のない世界」の実現に「核兵器を使用した唯一の核保有国として、米国には行動すべき道義的責任がある」と述べた。「核兵器のない世界」を求める世論が大きな流れとなりつつある今こそ、唯一の被爆国として国際的な流れを本流にしていく責務がある。 区として政府に対し、被爆国の政府として核兵器廃絶の国際交渉を国際社会に呼びかけ、開始するためのイニシアチブをとるよう要請すべきです。(09 2定 大滝実 代表質問 )