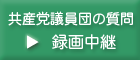東日本大震災で救援活動等に奔走する中、多くの消防団員が殉職、行方不明になりました。殉職された方々には、公務災害補償の認定が行われました。保障されても命がもどるわけではないので、家族のみなさんのお気持ちはいかばかりか、お察しいたします。一方、福祉共済制度は、殉職者が多数でたため、支払準備金を取り崩してもこれまでの共済金を支払うことが困難なため、弔慰金と重度障害見舞金2300万円を1100万円に減額、弔慰救済金を不支給にしました。大規模災害で消防団の方々が殉職されることがないよう、万全の対策が求められていますが、万が一の際、共済制度で決められた弔慰金等が支給できないことがないよう、福祉共済制度に国の財政支援を求めるべきです。 (14 1定 熊田議員)
|
||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||




|
||||||||||||||||||
| Copyright © 2010 Minato_kugidan All Right Reserved 日本共産党港区議団 〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25 TEL:03-3578-2945 FAX:03-3578-2947 Eメールアドレス: |