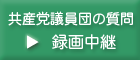北青山2丁目の公務員宿舎は民間マンションが完成。南青山6丁目の建設省青山住宅・学生寮・建設共済会館の跡地は大きなマンションが完成。南青山2丁目・都営住宅跡地は三井不動産がマンション建設中。南青山5丁目・公務員青山住宅は三菱地所が高級マンション建設中。南青山1丁目・都営住宅跡地は隣地と一体的に開発が進んでいます(都交通局所有・73年の定期借地権付きで日本土地建物㈱に貸付)。 多くの国有地や都有地が大手不動産に提供されています。
赤坂7丁目・都営住宅跡地は更地のまま。閉鎖されたままの関東財務局青山住宅(南青山2丁目)などもあります。さらに、南青山4丁目のホテルフロラシオン(教職員組合共済会)も昨年12月末で閉鎖になりました。農林省の南青山会館・宿舎(南青山5丁目・宿舎は昨年)も2月末で閉鎖。解体が始まっています。これらはほんの一部だと思います。放置しておけば、公有地が、大企業のもうけのために提供されかねません。
例えば、区立保育園や特養ホームをはじめとする区施設等の建設用地、首都直下地震の発生確率が高まっているときだけに、国や東京都から低廉な価格で購入する、借りるなどして近隣住民が避難できるように芝生公園や広場として確保する。また、国、東京都にも、防災上の観点から空地として確保するよう要求することを求めます。
白金二丁目の都職員住宅跡地は、東京都から購入する、借りるなどして、防災公園や区民要望の強い福祉施設としての活用を進めるべきです。 (15 2定 いのくま議員)