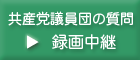難病に対する医療費助成制度の改定により、今年1月から医療費の助成を受けられる対象が拡大されました。7月1日に追加指定をされた難病を含めると、従来の56疾病から306疾病となりました。
一方で患者の自己負担の割合や負担の上限額が変わったことにより、これまで医療費助成を受けていた人のなかに負担が増えた方が出ています。とりわけ所得の少ない人に新たな負担が発生していることは深刻です。
住民税非課税者は従来自己負担がありませんでしたが、本人の年収が80万円までは月2500円、80万円を超えれば月5000円を負担しなければならなくなりました。区内でも250人余りの人に新たな負担が発生しました。
難病患者の方からは「治療のためさまざまな支出があるうえに、新たな毎月の負担が増えることは家計に大きな影響となっている」との声が寄せられています。
従来の受給者にとって「助成対象が広がり、多くの人が助かっているのだから制度維持のため負担を」と言われれば意見を言えないのが実情です。 住民税非課税者の難病医療費自己負担は、従来通り無料とするよう区の助成制度を設けるべきです。 (15 3定 大滝議員)