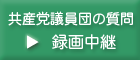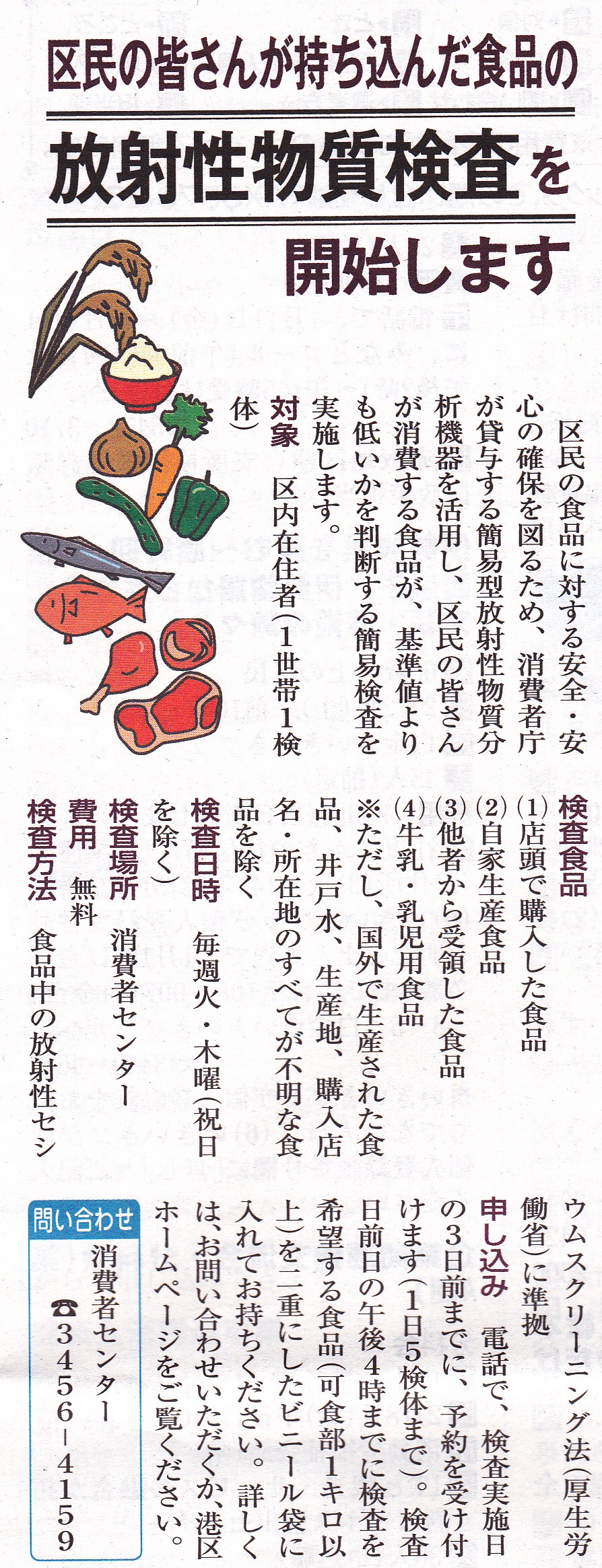2011年度決算特別委員会で、わが党議員の決算等審査意見書に対する質問で「住民基本台帳システムによる証明発行業務を委託しているが、個人情報の漏洩が危惧される業務委託は止めるべきと考えるが」と伺ったのに対し、監査委員は「受託した事業者が区民の住所、氏名、家族構成はもちろん、発行する証明によっては婚姻や養子関係、収入の総額と内容、所得額、納税状況なども見ることができる状態となっている」「個人情報の取り扱い範囲はリスクを十分に検討すべき」と答えました。 今年度から芝、高輪の総合支所で窓口業務の一部委託が始まり、来年度は全ての総合支所で行う計画ですが、審査意見書で「部分的に限定される環境にない個人情報の取り扱いは区が責任を持って行うことが安全面においてよりいっそう堅実である」と指摘されたものです。残念ながら、この指摘が正しかったと言うべき事件が発覚しました。 船橋市の非常勤職員が10年前から、住民の住所や生年月日、勤務先や年収、離婚歴などを調べ探偵業者に漏らし報酬を受け取っていたとして逮捕され、市役所が家宅捜索されました。区が委託する証明発行業務は37種に及ぶもので、個人情報のほとんどが明らかとなります。区にとって個人情報保護は危機管理の最も敏感な部分であり、漏洩は区民の信頼を失うだけでなく、犯罪に利用されれば凶器にもなります。個人情報保護規定や誓約書があるから安心できるというのでは、安全神話を振りまき大事故に至った福島第一原発と同じ道を繰り返すことになりかねません。総合支所の窓口業務委託は止めるべきです。 (12 4定 沖島議員)
リストラ、派遣切りなどで生活がますます深刻になり、私たちの所にも生活相談が増えています。相談の内容も深刻で、仕事、医療、介護、国保、教育、子育て、住宅など、たくさんの問題が複雑に絡み合い、生活保護だけでは解決しえない問題もあります。私たちの今までの質問で、区は「現状で対応する」といっていますが、相談者に親身になって相談にのり、どのような悩みでも、どうすれば解決の糸口ができるのか、相談者に応えることが必要なのに、役所の縦割り行政のなか、相談者はいくつもの部所をまわらなければならないことにもなっています。仕事、生活の問題など、解決にはスピードが要求されます。だからこそ、専門の総合相談窓口が必要です。相談者に親身に相談にのり、問題を早く的確に解決するために、何でも相談できる総合相談窓口を設置すべきです。 (12 4定 沖島議員)
区長は、党区議団が増税中止を「国に求めるよう」に要請しても、「消費税の増税を実施しないよう国に申し入れはしない」、「区民生活や区政に与える影響等の情報収集に努めるとともに、今後とも国の動向を注視していく」と、区民や商店・中小企業の置かれた実態をまったく省みないひどい態度です。消費税が増税されたら「商売を続けられない」、年金を減らされた上に消費税増税では「生活ができない」など、悲鳴が上がっています。区民生活に与える影響の情報といいますが、一体どんな情報を集めるというのでしょうか。消費税増税が国会で決まったとたん、マスコミが様々な試算を報道していますから、今更情報収集など必要ないはずです。消費税に頼らない別の途があります。日本共産党が提案している「経済提言」です。社会保障を再生・充実させながら、税金の無駄遣いの一掃や、富裕層や大企業に応分の負担を求める「応能負担」の税制を提案しています。同時に、国民の所得を増やすことを提言しています。区民生活と商店・中小企業の経営を破壊し、日本経済を破綻に導く、消費税増税の中止を国に求めるべきです。増大する生活保護受給者にも消費税増税は重くのしかかる。
このことを踏まえて、国に中止を要望してもらいたい。 (12 4定 沖島議員)
白金・三田・高輪地域は、京浜工業地帯の発生の地です。かつて1960年代は、町まちから機械の音が絶えませんでした。ところがバブル期には、地価の高騰等で工場が大田区に越したり、後継者難で廃業するところが相次ぎました。今では、不景気の中、「数が少ない試作品の仕事が多く、急ぎの仕事しかない」という人や、「最盛期の2割しか仕事がない」という経営者もいます。こうした中、「ものづくりを次世代へ」と、16日のNHK Eテレで、港区の町工場が紹介されました。昔懐かしい豆腐屋ラッパの復活の物語です。港区の楽器屋さんと、旋盤屋さん、板金屋さんが力を合わせ、豆腐屋ラッパを作り、そのラッパが東北の被災地の豆腐屋さんで使われ、仮設住宅の人を励ましているというのです。ラッパの音を出すため音楽大学の力も借りました。熟練工の巧みな技、1ミリ以下で勝負する技術の紹介、息子が跡を継ぎ、後継者が育っていることなどが紹介されました。私はこのテレビをみて町工場がこの港区にも「どっこい生きている。がんばっている」という感じをもちました。このラッパは、先日開かれた「港区ものづくり・商業観光フェアでも」紹介され、大勢の子供達がラッパを吹き楽しんでいました。景気が回復せず、大企業の海外でのものづくりが盛んになった今、私たちに希望をもたらせてくれるこうした事業に、区は光を与える必要があります。産業振興には、工業関係だけではなく、商業、観光などのたくさんの事業があります。不況で大変な時期だからこそ、事業者などと協力し、お互いに知恵を出し合い、具体的な施策を生み出すことが必要です。にもかかわらず、産業振興課、経営支援担当課は課長が1人となり体制が縮小されました。課長は2人体制に戻すべきです。せっかくいいプランがあっても施策の推進体制がありません。2008年度の「第2次港区産業振興プラン」では、「(仮称)港区産業振興センターの整備」を掲げ、21年度設計、22年度完成となっていますが、その目処は立っていません。事業内容の変更等も考えているようですが、そうであればなおのこと、推進体制の整備を図るべきです。また産業振興のための施策の推進を図るため、区内中小業者などの声を直接聞く機会、「第2次港区産業振興プラン」で掲げた「(仮)港区産業振興推進会議」を設立すべきです。 (12 4定 沖島議員)
高齢者も小さい子ども連れでも、安心して外出ができる、買い物にでかけられる、散歩ができる、観光客にもアピールできる、こんなまちづくりをめざして、歩道などにベンチの設置をすすめるべきです。設置するベンチも、あきる野市や、木材の活用の協定を結んでいる自治体の間伐材などの利用も検討し、ベンチに市名や町名を記入することで、区とのつながりを知ってもらうことにもなります。何よりも、高齢者や子育て世代が安心して出かけられるやさしいまちになります。人々がまちにでることで、健康を維持することになり、商店やまちの活気にもつながります。国や都にも協力をお願いし、高輪地区の「止まり木のある道路づくり」にとどめず、全区的に設置可能なところから、計画を進めるべきです。 (12 4定 風見議員)
わが党区議団は、エコノミークラス症候群をおこさないため、避難所に簡易ベッドを備えるよう提案を続けた結果、今年度510台の購入を決め、12月には納入するとのことです。一番のネックが保管場所の問題です。今回の購入に当たっても、いろいろと検討して、高齢者が使いやすいものを選んだそうです。さらに、来年度の購入にむけ、担当者を中心により良いものを検討していると聞きました。今注目され始めているのが「段ボールベッド」です。東日本大震災の避難所等でも使われ、血栓がなくなったり、減少するなど効果をあげています。「段ボールベッド」の良いところは、メーカーと「防災協定」を結び、災害時に緊急製造、搬送してもらえることです。災害時の道路事情などを考えれば、一定の備蓄は必要とは思いますが、保管場所の心配がないことです。今後も導入を進めるのですから、「段ボールベッド」についても検討すべきです。 (12 4定 風見議員)
日本最初の海水浴場は、1885年(明治18年)に神奈川県大磯(照ヶ崎)海岸に初代陸軍軍医総監をつとめた松本順によって開かれたとして、現地には「日本最初の海水浴場発祥地」と書かれた標識と石碑があります。 しかし、先日の新聞に、その7年前1878年(明治11年)に芝浦に海水浴場を開設する届けが旧東京府に提出されていたとの記事が掲載されました。すでに、 芝浦港南地区30周年記念誌「わたしたちのまちベイエリア」には、「1872年(明治5年)新橋・横浜間の鉄道敷設が完成。風光明媚な海岸であることに着目して、沿線に温泉旅館を経営するものが現れた。さらに料理屋や料亭、旅館、海水浴場や海水温泉などが芝浜から本芝にかけて数多く出現した」と明治初期に海水浴場が開設されたことが紹介されていましたが、今回の記録発見により時期が明確にされたことになります。記録によれば、旧東京市の編さんした史料集「東京市史稿」の中に、明治11年7月 に医者の鐘ヶ江晴朝が芝新濱町貳番地(現在の芝浦1丁目)に海水浴場の開設を申請しています。新聞では、申請文書や府の許可証、海水浴場の図面、開設届けが掲載されていると報じています。日本初の海水浴場として記録も場所もはっきりしています。これまで大磯海岸では日本初の海水浴場としてPRし集客を図ってきたのですから、港区も表示板などを設置し、ベイエリアの魅力の一つとしてPRを図っていくべきではないでしょうか。 (12 4定 沖島議員)
浜松町駅西口計画は、「都市再生特別地区」の指定で、*用途地域及び特別用途地域による用途制限、*用途地域による容積率制限、*斜線制限、*高度地区による高さ制限、*日影規制 がすべてなくなり、天井知らずになります。都市計画も事業者が提案したものを区がチェックして、区の計画として提案します。世界貿易センタービルディングや、国際興業などが提案した計画と一字一句違わないものが、区の「原案」、「案」として決められています。事業者言いなりです。200メートルもの超高層ビルが2棟も建つもので、基準容積率が612%なのに、計画では1120%と、1.83倍の容積です。「特別地区」はなんでもありで、大企業の「もうけ」を保障する以外のなにものでもありません。浜松町西口地区計画(案)の目標で「旧芝離宮恩賜庭園や大門通りの街並みとの調和に配慮」とか、整備の方針で「大門通りや旧芝離宮恩賜庭園等、周辺市街地と調和した魅力ある都市景観の形成」と言いながら、200メートルもの超高層ビルを2棟も建てる計画、まったく矛盾しています。区長はこの計画を推進しようとしています。一方、環境影響評価書(案)に対する区長の意見は、「大門通りの景観や旧芝離宮恩賜庭園からの景観について、圧迫感等の軽減に努めること」と、景観を問題にしています。当初案は「防風植栽が適切に生育しないおそれがある」こと。都知事への意見では、「評価地点を追加するとともに、良好な風環境の実現のため、関係者間での協議を」と、風害も問題にしています。200メートルもの超高層ビルを建てるから景観や、風害が問題になるのです。環境影響評価書(案)で危惧する問題を解決することができる立場にいるのが区長です。事業者に超高層ビルの計画の見直しを求めるべきです。 (12 4定 沖島議員)
今年度から武道の必修化にともない、柔道を選択する学校と、剣道を選択する学校とがあります。剣道の防具は、当然学校で用意します。ところが柔道着については、柔道をやる8中学校のうち、5中学校では、学校で用意しています(一部個人購入もあり)。 学校による対応が異なっており、保護者負担の公平性を欠いています。剣道を選ぶ学校と柔道を選ぶ学校間の保護者間の不公平も生じます。 必要着数のすべてを教育委員会で用意すべきです。また、ケガをしないよう安全な指導を徹底することを求めます。 ( 12 4定 風見議員)
先の決算委員会で、「待機児童解消に区が責任を持つこと。質を低下させないための区の立場をあきらかにすべき」との私の質問に、区は「待機児童解消に取り組むとともに、保護者が安心して、保育園に子どもを預けることができるよう、保育の質を確保していく」と答弁しています。私は、待機児童解消と保育の質の確保は、区が責任を持って認可保育園を建設することで解決に向かうと思いますがいかがか。待機児童解消に見合った認可保育園を建設すべきです。 (12 4定 沖島議員)