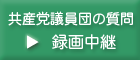党区議団の提案で、現在18小学校、10の中学校と、箱根にこにこ高原学園でPPSと契約し、一定の経費節減効果もでています。新聞報道によると、「東京都は今秋をめどに、都の所有する約300施設の電力契約先を東京電力から新電力に切り替える方針を固めた。既に約30施設で契約しているが、10倍に増やし、一年間で10億円程度の経費節減を予定している」との内容です。東日本大震災から2年3ヶ月が過ぎようとしています。地震と津波で爆発、崩壊した福島第1原発は、「収束」どころか、メルトダウンした核燃料や使用済み核燃料を冷やした冷却水の処理さえままなりません。原発と人類は共存できないことがますます明らかとなっています。日本列島全体が地震列島といわれ、東日本大震災規模の地震がいつ、どこで起きても不思議でないといわれます。福島原発の事故原因さえ明らかでない中、再稼働などとんでもないことですし、危険な原発を他国に売り込むなど許される話ではありません。経費節減とあわせ、原発依存から脱却するため、できるところから、東京電力との契約から、特定規模電気事業者(PPS)に切り替えるべきです。 (13 2定 風見議員)
区の制度である心身障害者福祉手当は、心身障害者等に手当を支給することによって心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的として1972年に開始された事業です。しかし、2000年の第4回定例会で、わが党以外の賛成多数によって、65歳以上の新規認定が廃止されてしまいました。条例改正の提案理由として「手当の支給開始当時と比べ年金制度の充実、国の手当制度の創設、介護保険制度の実施など社会状況が大きく変化した」としていましたが、実態は福祉の大幅切り捨て、年金給付の切り下げなどが進められてきました。 先日相談にこられた方は障害を負ったため仕事を失い、障害者手帳の交付を受けたときは65歳になっていたため福祉手当が受けられないと言われ、何回も相談しましたが「あなたが受けられる手当は何もありません」との冷たい対応で、少ない年金でどう暮らしたらいいのかと途方に暮れていました。さらに追い打ちをかけるのが昨年夏に成立した「社会保障制度改革推進法」で、社会保障制度を解体し、社会保障の営利市場化を進めようとするものです。 高齢化社会へと進む中、心身障害者の福祉の増進を図るために、65歳以上の福祉手当の新規認定を復活すべきです。 また、これまでも度々質問し、条例提案も行って精神障害者にも障害者福祉手当の支給を求めてきましたが、区はかたくなに拒否し続けてきました。これ以上差別を止め支給の決断をすべきです。答弁を求めます。 (13 2定 沖島議員)
2013年4月から障害者総合支援法が施行され、障害者手帳を持っていない難病患者も、新たに居宅介護や補装具、日常生活用具の給付などの障害者福祉サービスの利用が受けられるようになりました。新たに支援対象になる難病は130疾患の患者さんです。東京23区で新たな難病患者さんの申請者は7名、港区は1名です。申請者がほとんどいない背景には制度の周知が不十分との指摘があります。港区のホームページも障害者自立支援法のままで更新されていません。① 必要な方がサービスを受けられるように周知を図るべきです。② 難病医療費助成を受けている人などには、制度を紹介した個別通知をおこなうべきです。③ ホームページなども難病の患者さんの多くが見る「難病」や「健康・医療」などの項目からも障害者総合支援法の制度がわかるような工夫が必要です。 (13 2定 沖島議員)
国民年金制度は、未納分の「後納」は2年分しか認められておらず、納付期間が25年に満たず無年金となっている人を救済するため、年金確保支援法で昨年(2012年)10月から2015年9月までの間に限り、過去10年分にさかのぼって後納できるようになりました。しかし、保険料を一括納入しなければならず、保険料を工面できずに救済制度を利用できない高齢者が少なくありません。後納によって国民年金の受給資格ができるかどうか、死活問題です。また、支給対象期間の納付があっても、後納することによって受け取る年金額に大きな差が生じることになります。せっかくの救済制度ですから、お金の工面ができないために制度を利用できず、年金の受給資格を失うことがないよう、保険料支払いのための、資金貸付制度を創設すべきです。 (13 2定 風見議員)
自動車を持っていることを理由に生活保護を打ち切ったのは違法と認定した大阪地裁判決(山田亮裁判長、4月10日・大阪府枚方市は控訴を断念)が確定しました。現在の生活保護行政では、自動車の保有がきわめて限定的な場合にしか認められていません。何とか自動車を持ったまま生活保護の利用が認められても、通院以外に車に乗るなという指導指示がされることが少なくありません。自動車でしか移動できない障害者にとっては、こうした運用は、とても理不尽であり、生活に困った人たちが生活保護を利用することを妨げる非常に高いハードルとなっています。背景に、自動車保有を厳しく制限している(ように読める)厚生労働省保護課長通知があります。判決では、「通院等」の保有目的はあくまで「第一義的な基準」であって、医療や教育を目的にしない施設への定期的な訪問も「通所」に該当する場合もあり、目的などの要件が欠ける場合でも「特段の事情」があれば保有を容認する余地があるとしました。保有目的や保有の必要性を柔軟に解釈運用すべきことを明らかにしたのです。これからは、移動のためにどうしても必要であれば自動車を持ったまま生活保護を利用でき、通院以外の日常生活全般に自動車を利用してもかまわないのです。判決の趣旨を全国の福祉事務所に周知徹底することが求められています。国に対し、速やかに従来の保護課長通知を改正するか、正しい解釈指針を示す新たな通知を出すように要請すべきです。 (13 2定 風見議員)