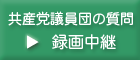国土交通省が計画している羽田空港国際線増便の新航路案については議会ごとに質問してきました。
都心区上空を通過する案は、騒音や落下物、事故などへの不安が強く住民に理解が得られていません。
昨年の決算特別委員会で羽田空港以外での落下物事故の状況を質問した際には、「過去10年間で、福岡空港で民間ヘリコプターからの部品落下が1件」とのことでした。ところが成田空港周辺では昨年、航空機の部品や氷塊の落下が4件もありました。うち2件は12月に報告され、国交省・成田空港事務所と成田国際空港が航空各社に落下物防止策を要請しています。
1月に品川と高輪を会場に開催された住民説明会は、実際は「説明会」とは名ばかりで、増便の必要性を強調し、新飛行経路案を押しつける内容でした。 飛行機の騒音については、実際の音に近いものが聞けるというヘッドホンが用意され、1~2回だけ聞くなら耐えられるかもしれませんが、毎日4時間繰り返されれば体調への影響が心配です。
国交省は、近年の集合住宅等は機密性も遮音性能も高いから室内ではほとんど気にならないと説明し、その音を聞かせるほどの念の入れようでした。国交省は、「飛行時間帯は外に出ないこと」、「遮音性の低い古い住宅には住まないように」と言わんばかりです。
騒音軽減策について、空港周辺の一定区域には防音工事に国の助成制度がありますが、空港の周りだけです。「着陸を開始する高度を引き上げることも考えられますが技術的検証が必要」とか、航空会社にさらに静かな航空機の使用を促すという他人任せで、やってみないとわからない、という無責任なものばかりです。
航空機事故や落下物などの安全対策についても、「安全対策を何重にも積み重ねてきた」「航空機、パイロット、地上部の各要素が相互に連携することで高水準の安全が実現されるよう努力している」と言うのみで、絶対安全を保障できるものではありません。
飛行コースは、万が一に事故が発生しても最小限の被害におさえることを大前提にすべきです。
区長は、予算編成方針の中で、誰もが住み慣れた地域で心豊かに生活できるよう地域福祉の充実を図りますと述べています。この立場からも、新航路案の撤回を国に要求するべきです。 (16 1定 いのくま議員)