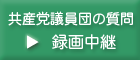障害児を育てる親が子育てと仕事を両立するのは、本当に大変です。我が子の障害を受け入れるのに親としての葛藤を乗り越え、仕事を続けるために保育園を探し、日々の生活に追われながら、手探り状態で子どものために何ができるのか模索しているのが実態です。区も2013年(H23年)10月に発達支援センター機能を障害者福祉課内に設置し、早期発見・早期対応、さらにはライフステージを通じた適切な支援の継続を目指す事業に取り組んでいます。保育園や保健所の乳幼児健診などとの連携により早期発見の仕組みがつくられ、相談件数も586件と昨年比で207件増えています。障害児を対象に日常生活の基本動作を指導したり、知識や技能の習得を支援したりする児童福祉法に基づく児童発達支援センターなども整備されるようになり、ようやく支援の輪が広がりつつあります。Aさんは障害のあるお子さんを抱えながら、子育てと仕事を両立しています。子どもの発達とともに、今この子に何ができるのか、悩みながら本当に手探り状態です。どの障害児の親にもいえることです。Aさんの子どもさんにはたくさんの専門家が係わっています。医師や保育士、支所の障害担当の職員、子ども寮育パオの職員、都の寮育センターの職員等々です。これだけ多くの専門家が係わりながら、保護者に対して、それぞれの分野で支援をしていますが、横の連携がとれていません。 Aさんから相談を受けて、区の保育担当と、障害の発達支援センターの職員の方にお母さんの思いを聞いていただきました。子どものために時間を作っていただいて、とても感謝していました。担当者も早速にケース会議を開く準備に取りかかっているとのことです。「発達障害者支援」の冊子でも、今後は、発見から相談・支援へつなげていくことや、支援を行う事業者等との連携協力のあり方が課題だと述べているように、一人一人に寄り添った支援を連携して行うためにも、発達支援センターが中心になって、ケース会議を開いて連携した支援ができるようにすべきです。 (14 3定 熊田議員)
小学校のRAS38名中、司書資格を持っている人は小学校9名、司書教諭の資格を持っている人は小学校7名、中学校のRAS20名中4名が司書資格を持ち、司書教諭は5名です。半数近くの人が専門的な資格を持っている方です。先の定例会でもRASの職員待遇を求めましたが、教育長は「地域の方とともに学校図書館を支える有償ボランティアとしての、リーディングアドバイザリースタッフの取組を充実させていく」と答弁しています。専門的な資格を持っている人や、RASの仕事に意欲を持って働いている人が多いのに、いつまでも有償ボランティア扱いでいいはずはありません。港区が、職員待遇でないため、司書資格や教員免許を持った人、学校図書館の仕事に意欲を持って取り組んでいるRASは、活動条件のよい他自治体に移っているという声も聞きます。さらによりよい学校図書館にするために、リーディングアドバイザリースタッフは職員待遇とすること。答弁を求めます。 (14 4定 沖島議員)
就学援助制度は、憲法26条の教育を受ける権利を保障するもので、学校教育法第19条「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない」と定めています。働く人たちの賃金が下がりつづける一方、物価の値上がりで暮らしが大変になっているだけに就学援助の必要性が高まっています。こうした中で国民の長年の運動を通じてクラブ活動費、PTA会費、生徒会費が2010年度から国の補助対象品目になりました。しかし港区では対象にしていません。これまでも対象とするよう求めてきましたが「他の自治体の動向等も踏まえ検討する」としていました。現在、23区内において、クラブ活動費については補助対象とするのが半数近くに広がっています。港区は都内でもとりわけ諸物価の高い地域でもあるので、3つの会費を率先して補助対象とすべきです。 (14 3定 大滝議員)
2013年5月に発表された港区政策創造研究所の「75歳以上高齢者を含む2人世帯の生活に関する調査報告書」では、住宅の困りごとで、「老朽化している」が19.7%、「家賃・税金の負担が大きい」16.5%、「階段の昇り降りが大変」とつづき、「いつまでここに住めるか不安」が1割を超えています。一方、家主側も深刻で、孤立死などから高齢者の入居を制限するというものです。国土交通省が2010年、日本賃貸住宅管理協会の協力を得て実施した「民間賃貸住宅の管理状況調査」によると、複数回答で「単身の高齢者は不可」が40.6%、「高齢者のみの世帯は不可」が34.9%となっています。港区の都営住宅の高齢者用の地元割り当ての応募状況は、募集1戸に対し83倍から102倍、区立の高齢者集合住宅(ピア白金、フィオーレ白金、はなみずき白金、はなみずき三田)の空き家登録数8名に対し抽選倍率は約15倍、入居できるのは年間で2名から4名です。昨年10月に行われたシティハイツ芝浦(区営)は、21戸の募集に対し、370件の応募、350人に近い人たちが入れなかったことになります。 私たちは、今までも高齢者住宅の必要性を述べ質問してきましたが、区は「民間事業者の参入を促進し、サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの設置を進めてまいります」と答弁するのみです。サービス付き高齢者向け住宅やグループホームを否定するものではありませんが、低所得者には家賃が高すぎて入れません。高齢者の置かれている実態をふまえ、いきいき計画で中断した高齢者集合住宅を建設すること。答弁を求めます。文京区は、来年度から高齢者の入居を受け入れる家主さんへの支援を打ち出しました。月最大2万円を補助するというものです。しかもシルバーピア住宅に配置されている生活協力員のような方(生活援助員)を登録物件の高齢者宅に派遣をするというものです。高齢者を受け入れる家主さんへの支援策を行うこと。高齢者世帯等居住安定支援事業を復活させること。高齢者の民間賃貸住宅家賃助成を行うこと。それぞれ求めます。 (15 1定 熊田議員)